はじめに
西武池袋線の高麗駅や巾着田から正面に仰がれる堂々たる山容の「日和田山」(ひわださん)。
標高305.1㍍の低山だが、男坂には鎖場もあり、岩場を登り切った金刀比羅神社(ことひらじんじゃ)二の鳥居から広がる展望は素晴らしいの一言。
なかでも、眼下に見下ろすことのできる巾着田の全貌、そして巾着田を囲むように屈曲した高麗川の向こうに低くうずくまる高麗丘陵が印象的。
もっとも、高麗丘陵は西武鉄道の2つのゴルフ場(武蔵丘ゴルフコース、新武蔵丘ゴルフコース)によって、その大半が占められてしまったのが残念。
今では、ゴルフ場に挟まれた2つのハイキングコース(高麗峠~巾着田、高麗峠~宮沢湖)を残すのみ。
二の鳥居から元宿の信仰を集める金刀比羅神社社殿をへて、僅かな登りで、305.1㍍4等三角点(点名「日和田山」)と、聖天院35世隆敬が江戸時代に建立した宝篋印塔がある山頂につく。
山頂からは、それまでの岩場もある荒々しい様相とは対照的に、なだらかな尾根となり、NTT電波塔のある高指山(たかさしやま:『武蔵通志』は「高佐須山」と表記)から山上集落・駒高(日高市大字高麗本郷)へ展望に恵まれたのびやかな尾根歩きとなる。
『新編武蔵風土記稿』高麗郡高麗本郷村の条では、日和田山は高麗本郷・清流・梅原・栗坪4村の入会秣場(4つの村の住民が共同で利用できる草地、および草地と小灌木が混在した土地)であると記している。
秣場から刈り取った草木は、馬・牛の飼料、田畑の肥料、家庭燃料として利用されていた。
そんな秣場の名残が感じられる一帯である。
このように荒々しい岩場とある南面と、秣場の名残のある穏やかな北面という対照的な2つの顔をもつ日和田山は、山麓の巾着田とセットで、日高市を代表する観光スポットであり、年間を通して多くのハイカーや観光客が押し寄せる。
このポピュラーな山の山名に関し、マニアックな視点から深掘りしてみたい。
日和田山の山名考証
「日和田」とは「日当たりの良い和田」の意味。
そこで「和田」(わだ)について、鏡味完二・鏡味明克『地名の語源』(角川書店、1977年)を見ると、「河の曲流部などの、やや広い円みのある平地」で、「そこが必ずしも田であるを要しない」とある。
これを日和田山周辺にあてはめると、巾着田が地形的に「和田」に符合することに気づく。
巾着田こそ、「高麗川の曲流部に囲まれた平地=田」にほかならない。
つまり、日和田山は巾着田(水田)における農耕信仰の象徴的な山であり、そこから日和田山の名が生まれたのではないだろうか。
日和田山と水の神である金刀比羅神社がセットになっているというのも、この推測を裏付ける根拠であるように思われる。
狭義の日和田山と広義の日和田山
(略図)広義の日和田山=狭義の日和田山(雄日和田)+小日和田(雌日和田)(出典)日高市ホームページの「日和田山拡大図」に加筆

(略図)狭義の日和田山と広義の日和田山
-1024x781.jpg)
高麗駅や巾着田から日和田山を眺めると、一段と高い山頂の東に小さなピークがあり、そこから一気に標高を落としているさまが良く分かる。
とくに巾着田からみた場合、左側の日和田山最高点(山頂)から少しくだったあとは、ほぼ平坦な尾根が続き、その尾根が山麓に向け急激に高度を下げる直前にピークのようなものが確認できる。
この日和田山の東にある小ピークを、大字清流では「小日和田」(こひわだ)と呼び、小日和田の背後にある一段と高い「日和田山」と区別している。
ここでは、日和田山を305.1㍍4等三角点に限定している。
その意味で、305.1㍍三角点峰を「狭義の日和田山」と呼びことができる。
これに対し、『角川地名大辞典11 埼玉県』(角川書店、1980年」に、次のような記述がある。
「(日和田山の)山頂は双耳峰をなし、東峰を雌日和田、西峰を雄日和田といい、聖天院35世隆敬の建てた宝篋印塔がある」
これによれば、私たちが日和田山と呼んでいるのは日和田山の西峰であり、「雄日和田」(おひわだ)という。
そして東峰が「雌日和田」(めひわだ)であり、「雄日和田」「雌日和田」の総称こそ「日和田山」ということになる。
これが「広義の日和田山」である。
では、「雌日和田」(東峰)はどこなのだろうか。
先に高麗駅や巾着田から眺めた日和田山について語ったが、双耳峰というほど顕著ではないが、たしかに一段と高い西峰(雄日和田)と、平頂稜の東端にちょこんと突き上げている「小日和田」が確認できる。
つまり、『角川地名大辞典11 埼玉県』の記述にしたがうかぎり、「雌日和田」は「小日和田」以外には考えにくい。
「雌日和田」(日和田山東峰)を「小日和田」の位置としているのが、『新装版 奥武蔵登山詳細図』(吉備人出版、2022年)である。
『新装版 奥武蔵詳細地図』では、日和田山より東に寄った地点(=小日和田)に「雌日和田山」の名を記し、標高300㍍としている。
だが、詳細図では、日和田山を「雄日和田」としていないし、「雌日和田山」ではなく「雌日和田」が正しい。
「雌日和田」(=小日和田)の標高を300㍍としているが、2万5千分の1地形図「飯能」(2016年7月調製、2016年11月1日発行)を見る限り、260㍍圏が正しい。
「詳細図」の影響で、ハイカーの間に「雌日和田山」の名が広がり、最近では日和田山(雄日和田)に登る前に、山頂手前から東に踏跡をたどり、雌日和田(小日和田)に寄る人も増えてきた。
だが残念なことに、雌日和田(小日和田)山頂に「雌日和田山」と書かれた私設の山名表示版が設置されてしまったため、誤った名称(雌日和田山)が広まったのは残念である。
以上、狭義の日和田山(日和田山と小日和田を区別)と広義の日和田山(西峰=雄日和田、東峰=雌日和田両者の総称名が日和田山)を区別するという少々煩雑な議論をしてきた。
改めて整理すると、広義の日和田山=狭義の日和田山(雄日和田)+小日和田(雌日和田)となる。
気になるのは、地元の大字高麗本郷で「雄日和田」「雌日和田」の呼称が今でも使われているのかどうかという点である。
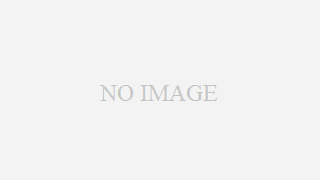

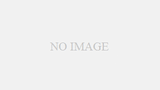
コメント