比企・外秩父の気になる山や峠を手っ取り早く知りたい方のために、「比企・外秩父の山徹底研究」14回のエッセンスに未紹介の山を加えたコンプリートな小辞典をつくってみました。
山名については、なるべく山名の由来を記すことにし、峠名・巨石名のほか、重要な地点名も数カ所取り上げました。
「愛宕山」「物見山」など同名の山がいくつもある場合は、標高の高い順に掲載しています。
以下凡例を示しますが、山名・峠名についてもっと詳しく知りたい方は「徹底研究」の該当回を参照してください。
また、各項目をカバーする国土地理院発行2万5千分の1地形図を挙げておきますので、2万5千分の1地形図および昭文社・山と高原地図23『奥武蔵・秩父』(奥武蔵研究会調査執筆)を見ながら読み進めると、良く分かるでしょう。
誤りを発見したり、疑問点があれば、「問い合わせ」を使ってご指摘いただければ幸いです。
今回は「た行」です。
(凡例)
見出し
かさやま 笠山(小川町・東秩父村)
本文
比企郡小川町腰越・秩父郡東秩父村白石
第8回「笠山・堂平山」(比企外秩父徹底研究の回数)
2万5千分の1地形図「安戸」
説明文
○○○・・・
それでは、比企・外秩父のディープなワールドに浸ってください。
た
だいにちやま 大日山(ときがわ町)
比企郡ときがわ町日影
第6回「雷電山・御岳山・大峰とその周辺」
2万5千分の1地形図「安戸」
ときがわ町日影の雀川源流域にあり、源流北側の行風山(332㍍独標)の南に対峙している330㍍圏ピーク。
昔、山頂に大日如来様(お大日様)が祀られていたことから、大字日影の小北(こぎた)集落の古老のなかには、この山を「お大日様」あるいは「大日山」と呼ぶ人もいる。
現在、山頂には石積みの上に石碑が残されているが、これが「お大日様」の名残りである(「お大日様」の項目を参照)。
だいにちやま 大日山(小川町)
比企郡小川町下里
第4回「仙元丘陵」
2万5千分の1地形図「武蔵小川」
小川町青山の仙元山から城山(青山城址・割谷城址)へ南に続く仙元丘陵。
その仙元丘陵が槻川の流れに沿ってL字型に東に方向を変える付近の北東山麓に、小川町下里1区の割谷(わりや)地区がある。
下里側からは、まず割谷橋で槻川を渡る。
割谷は支流の沢名であり、同時に集落名でもある。
槻川から離れて仙元丘陵に深く食い込んでいる沢(割谷)の下流沿いに6軒(1987年当時)の人家が点在する。
さて、割谷橋を渡り、割谷集落に入って、最初に右岸(左手)から流入する千木沢(千騎沢)添いの道を割谷沿いの林道から分かれて少し登ると、まもなく右手に巨大な岩壁が現われる。
この岩壁こそ「大日山」(だいにちやま)である。
この付近には珍しい大きな岩場で、基部から3㍍ぐらいのところに「猿田彦太神」の石碑が祀られている。
さらに、30㍍ほどの岩場上部の岩穴に大日如来像が祀られている。
大地如来像はオーバーハングした岩場上部の穴に安置されているので、近づくのは容易ではない。
岩場の上からザイルで確保してくだって探るしかないが、実際に見た方の話によると、粉をひく引き臼ぐらいの大きさの蓮の花を台座にとした座高50センチほどの可愛らしい石像であったという。
大日山は、岩壁がオーバーハングしたようになっていて、今にも上から落ちてきそうだが、逆に山仕事で急な雨に降られたとき、雨宿りするのに絶好の隠れ場所であった。
大日様(大日如来)が守ってくれるので、岩が崩れ落ちることはないと信じられていた。
割谷の集落では、暮れには門松、小正月(1月4日)には削り花を大日山に供えていた。
かつては門松、削り花を各戸について二本ずる、一つは猿田彦太神に、もうひとつを大日如来様に供えていた。
しかし、岩場を登るのが命がけなので、今では(1987年当時)、千木沢の入口に門松や削り花を二本ずつ供えるように簡略化されている。
なお、昭文社山と高原地図23『奥武蔵・秩父』(2025年版)では、仙元尾根が東に方向を変えたところにある252.6㍍4等三角点(点名「下:しも」)に「大日山」と表記している。
また、252.6㍍4等三角点峰には「大日山」と書かれた大きな私設の山名表示板が建てられている。
しかし、いずれも誤りである。
たいらがやのさんかくてん 平萱の三角点(小川町・ときがわ町)
小川町腰越、ときがわ町西平
第9回「慈光寺と都幾山・金嶽・士峰山」
2万5千分の1地形図「安戸」
慈光寺・霊山院裏の金嶽(463㍍独標)から冠岩を経由する小川町とときがわ町との境界尾根上の539.4㍍3等三角点峰(点名「平萱」)。
昭文社山と高原地図23『奥武蔵・秩父』(2025年版)では「金嶽」と表示しているが、これは誤りである。
小川町側の赤木(腰越)では、小字名の「平萱」(たいらがや)から、文字通り点名どおり、「平萱の三角点」と呼称。
ときがわ町西平では、三角点付近に「風早」の小字名がある。
『新編武蔵風土記稿』比企郡平村の条に、「風早山 西北にあり」と記され、位置的に「平萱の三角点」と一致する。
その意味で、「平萱の三角点」の西平側の名称を「風早山」として構わないだろう(風早山の項を参照)。
たかがいやま 高谷山(東秩父村・秩父市)
秩父郡東秩父村白石・秩父市定峰
第8回「笠山・堂平山」
2万5千分の1地形図「安戸」
白石峠から定峰峠(新定峰峠・マジノタワ)に向かう、2つの大きな山がある。
最初が「川木沢ノ頭」(874㍍)。
次の大きな山容の828㍍独標が「高谷山」(たかがいやま)である。
大石真人氏は828㍍独標を「ハギノソリ」と呼び、「新定峰峠から川木沢の頭つらなる尾根上の明るい一峰で、将来、定峰峠・堂平山ハイキングコースでなじみになるところであろう」とされている(大石真人『マウンテン・ガイドブック・シリーズ8 奥武蔵』朋文堂、1960年版所収の「奥武蔵辞典-山名編-」)。
藤本一美氏も大石氏を踏襲し、828㍍独標を「萩ノソリ」としている(藤本一美『比企(外秩父)の山々』私家版、2018年)。
だが、『高篠村誌』(秩父市高篠公民館、1980年)所収の「高篠村略図」(同村の小字の地図)によると、「萩のソリ」(高篠村略図の表記名)は、山田村・栃谷村・定峰村の三村が明治22年(1889)に合併してできた高篠村(1957年に秩父市と合併)の東端(旧定峰村の区域)で、川木沢ノ頭~白石峠の小字名である。
そうなると、「萩のソリ」は、828㍍独標と距離が離れすぎているため、同峰の名称とするのには無理がある。
それ以上に重要なのは、東秩父村白石での聞き取りで、地元の古老が828㍍独標を「タカガヤ」と呼んでいた点である。
『新編武蔵風土記稿』秩父郡白石村の条でも、「高谷山 村の南にあり」と記している。
以上をふまえ、828㍍独標は無名峰でも「ハギノソリ」(萩ノソリ:萩のソリ)でもなく、地元呼称と古い地誌を重視し、高谷山(タカガヤ)と記載すべきであろう。
たかはた タカハタ(小川町・東秩父村)
比企郡小川町腰越・秩父郡東秩父村安戸
第7回「笠山前衛の山々」
2万5千分の1地形図「安戸」
高旗山・高畑山とも表記(読み方は、いずれも「たかはたやま」)。
帯沢川をはさんでリュウゴッパナ~ツルキリ~物見山の尾根と並行する笠山郡界尾根上の407.6㍍4等三角点ピーク(点名は「腰越」)。
笠山西峰から北に延びる比企郡と秩父郡の郡界尾根は、途中で方向を西に変え、さらに北東に変える。
「タカハタ」は最後の北東に方向を変えた郡界尾根上にある。
笠山郡界尾根は、同じく笠山に発する前衛の尾根のうち、観音山の尾根、リュウゴッパナの尾根が、前者は珪石の採掘、後者は林道の開通などにより、登山価値を失ってしまったなか、ハイカーに残された静かな尾根である。
タカハタの山名由来となっている次のような伝説がある。
昔、鉢形城の出城であった安戸城では、リュウゴッパナからの尾根上にある「物見山」に見張り櫓を置き、異変があったときには旗を立て、安戸城に知らせていた。
あるとき、旗が風で飛ばされ、タカハタ山頂の立ち木に引っかかった。
それ以来、この山を人々は「タカハタ」と呼ぶようになったという(東秩父村安戸の帯沢で採集)。
たかねやま 高根山(滑川町)
比企郡滑川町福田
第13回「大立山・二ノ宮山・高根山」
2万5千分の1地形図「三ヶ尻」
比企丘陵最北端に位置する105.1㍍3等三角点峰(点名「高根山」)。
大立山(滑川町中尾)、二ノ宮山(滑川町伊古)とともに、滑川町を代表する山である。
比企郡滑川町福田に属するが、旧大里郡江南町(現:熊谷市)小江川(おえがわ)との境界にも近い。
西側を除き、三方を高根カントリー倶楽部に囲まれている。
『武蔵通志』は、「高さ一千二百尺、福田村の北にあり、奮松林なりしが近時剪伐して、頂上に一叢を残す。四顧爽潤にして北は行田・熊谷等の市街を(中略)望むべし」と記す。
西面に刻まれた参道を登ると、中腹に「小高根さま」の小祠。
山頂の岩盤の上には「高根さま」(たかねさま)の祠がある。
藤本一美氏は、「超低山であっても周辺からみれば、ひと際目立つ高い尾根、峰の山ということで、滑川町上福田の人々に信仰され」と、山名を考察しておられる(藤本一美『比企(外秩父)の山々』私家版、2018年)。
東山麓の円正寺前ヤツ(約10戸)、円正寺後ヤツ(約10戸)、榎ヤツ(約5,6戸)(いずれも滑川町上福田)の人々が信仰。
高根さまの例祭は毎年4月24日。
役員は祭りの指図をする大役(数年間務める)と団子をつくる当番(一年交替)に分かれ、各ヤツごとに一名ずつ。
当日の朝8時頃に各ヤツの当の家に集まって、あらかじめ各戸から3合ずつ集めておいた米で団子をつくる、
なお、榎ヤツは山頂までの距離が遠いので、山頂に最も近い円正寺後ヤツの当番の家で一緒に団子をつくる。
つくった団子は昼過ぎに山頂に運びあげて、子どもが学校から帰ってくる14時頃から祭礼が始まる。
ところで昔、高根山の所有をめぐって、大里郡小江川村と比企郡福田村が争った。
しかし、円正寺不動庵の坊さんの計略で、高根山は福田村の分になった(現に、熊谷市と滑川町との境界よりもやや滑川町に入ったところが高根山頂)。
その争いの場が今でも「論証場」(ろんしょうば)の名で残っている(高根カントリー倶楽部内)。
熊谷市小江川の鎮守である高根神社は「古くは元高根(注:ヘリテイジゴルフコース南の高台付近)に鎮座したいたのを享保年間(1716~36)に現在地に遷座したものと伝えられる」(高根神社の説明板による)とある。
だが、小江川の古老のなかには、高根神社はもともと高根山にあったものを、福田村との境界争いに敗れ、現在地に移転したという人もいる。
その真偽のほどは定かではないが、境界騒動にまつわる逸話が今日でも上福田、小江川双方に伝わっているのは興味深い。
たかやま 高山(寄居町)
大里郡寄居町三品
第2回「官ノ倉西尾根とその周辺」
2万5千分の1地形図「寄居」
官ノ倉山から延々と続いた官ノ倉西尾根の終点(西端)に当たる277㍍独標。
寄居町三品(みしな)の背後に聳える山であり、麓には三品の鎮守・白鬚神社がある。
そして、三品をはさんで、車山と対峙している。
高山の名は、明治期の地誌『武蔵国郡村誌』『武蔵通志』にも見られる。
高山の名は、その名のとおり、寄居町三品付近では一番高い山という意味であろう。
『武蔵国郡村誌』男衾郡三科村の条に、「山上に高山社あり」とされているのが、高山石尊神社である。
高山石尊神社が祀られていることから、高山を石尊山とも呼ぶ。
最近、ハイカーの間では、高山を「三品石尊山」と読んでいるようである。
『武蔵国郡村誌』の高山社に関する記述を要約すると、「日本武尊が東征の際にこの山頂で憩い、石に腰掛けて四方を見渡した。その石を高山石尊神社として祀った」とある。
町田尚夫氏によると、「近世は願い事を叶えてくれる神様として信心され、戦前まで数多くの講が参拝した」という(町田尚夫『奥武蔵をたのしむ』さきたま出版会、2004年)。
高山石尊山様(高山石尊神社)の山開きは例年8月18日で、この日から当番が2人1組で山頂の灯籠に灯をともしに行った。
高山石尊神社の例祭は8月28日だが、山開き(8月18日)から世話人は講元の家に集まり、祭りの準備を進めた。
まず、前年度に記帳した人すべて(約100人)に呼出状を出す。
例祭の当日には「高山石尊神社神璽」と刷られたお札を配る。
祭りの当日、最後の準備として、山頂が狭いので、世話人は「お棚掛け」と呼ばれる桟敷をつくる。
当日には、白鬚神社境内につくられた公民館に収納された祭りに使われる道具一式をリレー方式で山頂に持ち上げた。
例祭の当日8月27日は午後2時から4時頃までがもっとも賑やかになるが、過去90年間で雨に降られたことは2回しかなかったという。
祭りには三品以外にも、西ノ入、秋山など近隣から多数の参拝者が訪れ、氏子以外にお金を出して祈願を申し込む人は100人近くにのぼったという。
平倉地区(寄居町西ノ入)では、梵天講が組織され、例祭(8月27日)の当日、石尊神社の御神木に幣束をつけた梵天を取り付けて祈願を行う習わしになっていた。
祭りが終了すると、世話人をはじめ氏子の人々は、一杯ひっかけながら山をくだり、公民館で夫日待ちを行った。
そして、お日待ちをしてもお金を毎年積み立て、昭和60年(1965)に高山山頂の石尊神社社殿を改修した。
これが現在の石尊神社奥社である。
では、なぜ山頂の神社が奥社になってしまったのか。
それは、住民の多くが高齢になり、高山山頂まで登るのが大変なので、麓の白鬚神社境内の「畠山重忠の乗り上げ石(ひずめ石)」に高山石尊神社を遷座しようという声が住民の間で強くなった。
いったんは「あくまでも高山山頂の高山石尊神社で祭りを行いたい」とする講元の主張がとおり、祭りは引き続き高山山頂で実施された、
しかし、その後再度「高山山頂の石尊神社で例祭を続けるのか、それとも住民の高齢化にともない、白鬚神社境内の「畠山重忠の乗り上げ石」に石尊様の本尊を移し、里で例祭を行うべきか」をめぐる論争が始まった。
その結果、最終的には1990年代になって、石尊神社本尊を白鬚神社境内の「畠山重忠の乗り上げ石」の上に遷座し、毎年8月27日の例祭は里で行われるようになった。
このときから、高山山頂の高山石尊神社は「奥社」に降格したのである。
高山山頂からは北側に「ラクダの背のような」(町田尚夫氏)コブを連ねた車山の特異な山容が印象的に望まれる。
たかんど たかんど山(寄居町)
大里郡寄居町富田(とみだ)
第14回「四ツ山(四津山)・物見山・堂ノ入山・たかんど」
2万5千分の1地形図「寄居」
2万5千分の1地形図「寄居」の右下に、東武東上線をはさんで巨大な「本田技研工業(株)埼玉製作所 完成車工場」(鷲丸山跡地)の東に対峙し、南は寄居カントリークラブ、そして北は押し寄せる住宅地に囲まれた丘陵地帯が存在している。
それが、北の「堂ノ入山」(171㍍独標:寄居町富田)と南の「たかんど」(193㍍独標:寄居町富田を結ぶ丘陵である。
このうち堂ノ入山は。「男衾自然公園」として、男衾桜(アーコレード)の名所として整備され、「たかんど」東側の湿地に「おぶすまトンボの里公園」がビオトープとして整備された。
「たかんど」は「たかんど山」ともいい、標高わずか193㍍の超低山だが、本田技研工業(株)寄居工場の建設により消失した「鷲丸山」(標高216㍍)に代わり、男衾地区の最高地点に躍り出た。
「たかんど」という名称は、文字通り、この付近でもっとも高いところを意味している
これまで未整備のヤブ山だったが、「おぶすまトンボの里公園」を整備した「寄居にトンボ公園を作る会」の手により、トンボの里公園からたかんどをへて、「男衾自然公園」へと回遊する道が整備された。
残念ながら、たかんど山頂は雑木に覆われ、展望は得られない。
しかし、「おぶすまトンボの里公園」から「たかんど」経由で堂ノ入山を中心とする「男衾自然公園」にまで歩けば、素晴らしい展望に加え、桜やカタクリなどの花を堪能することができる。
ち
ちくびやま 乳首山(東秩父村・寄居町)
秩父郡東秩父村坂本・大内沢・大里郡寄居町西ノ入
第2回「官ノ倉西尾根とその周辺」
2万5千分の1地形図「安戸」
官ノ倉西尾根の「細窪山」(421.2㍍3等三角点)西の比企郡・秩父郡・大里郡の三郡境界のピークと金山・君八山との中間にかつて存在していた364㍍峰。
山頂は凹地をはさんで二峰に分かれていて、それがあたかも女性の胸を連想させることから、東秩父村の坂本や大内沢では「乳首山」(ちくびやま)と呼ばれていた。
「チチクビヤマ」と発音する人もいる。
この山は鉢形城からみると、鬼門の方向にあたる。
そこで昔、ある人が鉢形城の財宝が埋まっていないかと掘ってみたところ、何も出てこなかった。
ところが、帰りに大雨に降られ、そのために病を得て亡くなってしまったという伝説が大内沢では残されている。
そういえば、乳首山から尾根続きの「金山」も、その山名由来について、鉢形落城のとき、埋蔵金をこの山に埋めたという伝説に起因している。
私が最初に乳首山を踏査した1986年当時、既に364㍍の山頂は削られ、削平された広大な広場と化していた。
その後、秩父鉱業(株)寄居鉱山所によるセメント用の砂岩の採掘はどんどん進み、2万5千分の1地形図「安戸」にも広大な採石場が広がり、官ノ倉西尾根は完全に寸断されてしまった。
ところで、韮塚一三郎編著『埼玉県伝説集成(中・歴史編)』(北辰図書出版、1973年)には、「チツクビ山」(埼玉県東秩父村坂本)の項で、先に述べたものと似た内容の伝説を収録している。
「大内沢の入口、坂本分にチツクビ山という高い山がある。虎岩のあるところである。このチツクビ山は忍城(あるいは鉢形城)が落城した時宝物を埋めたところといい、掘ると血の雨が降るという」
ちごいわ 稚児岩(寄居町)
大里郡寄居町西ノ入(五ノ坪地区)
初出
2万5千分の1地形図「寄居」「安戸」
官ノ倉西尾根北側の山林にあるヒスイ輝石(ジェダイト)を含む岩石の露頭。
「稚児岩」と呼ばれる伝説を踏めた大岩である。
場所は、寄居町西ノ入の五ノ坪地区。
八高線・折原駅から線路に沿って小川町方面に戻り、五ノ坪の集落に入る。
すぐに五ノ坪川に進行右側から支流(馬込と呼ばれる)が合流する。
ここで本流から分かれ、支流(馬込)に沿った林道を進み、舗装が切れた先で森林のなかに大きなヒスイ輝石(ジェダイト)を含む岩石の露頭が現われる。
これが稚児岩である。
ヒスイ輝石を含む岩石の露頭があるのは珍しいが、ここの岩石は、ヒスイ輝石50%、石英50%なので、ヒスイ輝石の純度は50%。
「ヒスイ」として宝石になるためには、ヒスイ輝石の純度90%以上が必要とされるので、残念ながら純度50%の稚児岩のヒスイ輝石・石英混合岩は「宝石」としての価値はない。
さて、五ノ坪で採集した稚児岩にまつわる伝説を紹介したい。
豊臣氏の総攻撃により鉢形城が落城したとき、当主・北条氏邦の側室が逃げてきて、この地で子どもを産み、その子に乳を飲ませたことから稚児岩と呼ばれるようになったという。
しかし、「広報よりい」(2010年10月号)を見ると、「稚児岩」にまつわる伝説はもっと複雑な内容である。そこで「正統説」を引用しておこう。
「昔、小河原城主・北条氏政(鉢形城主・北条氏邦の兄)の側近の青年武士が氏政夫人の美しい腰元の女性と心を通わせるようになり、女性は武士の子を身ごもりました。
2人のうわさを聞いた氏政は『不義はお家のご法度』ということで、2人は弟の氏邦が城主を務める鉢形城に預け幽閉することとしました。
生み月がせまった2人は密かに鉢形城を抜け出し、深沢川をさかのぼり、山中をさ迷っていたところ、女性は大きな岩の上で急に産気づき、そこで人知れず赤ん坊を産み落としました。
3人は産着も食べものもなく、途方に暮れていたところ、一人の農婦が通りかかりました。子細を聞いた農婦は深く同情し、家に招いて赤ん坊の世話から、2人の世話まで面倒を見てくれました。おかげで3人は元気を取り戻し、いずこへともなく旅立って行きました。
この赤ん坊が生まれたという岩は今でも『稚児岩』と呼ばれています」(「広報よりい」2010年10月号)
ちゃたてば 茶立場(茶屋跡:皆野町)
秩父郡皆野町三沢
第10回「新定峰峠・旧定峰峠・大霧山・粥新田峠」
2万5千分の1地形図「安戸」
大石真人氏は、「外秩父概念図」(『マウンテン・ガイドブック・シリーズ8 奥武蔵』朋文堂、1954年版所収)で、大霧山南の724㍍独標に「茶立場」と表記。
同氏は、『マウンテン・ガイドブック・シリーズ8 奥武蔵』(朋文堂、1960年版)所収の「奥武蔵辞典-山名編-」において、「茶立場 大霧山頂のすぐ南につらなる一峯であるが、現在ここには二子山という名の入った指導標が立っている」と、茶立場の山名を維持しつつ、「二子山」の別名に言及している。
同じ「奥武蔵辞典-山名編-」の「二子山」の項で、「二子山 大霧山の南方、里称茶立場の上に二子山と書いた指導標が立っている。大霧主峰とともに、二子状をなすのであろうか。あまり適当な名とは思えない」と、茶立場を地元呼称としつつ、二子山の「別称」については、疑問を呈している。
ところが、大石氏があとがきを書いている奥武蔵研究会『ブルーガイドブックス4 奥武蔵と比企丘陵』(実業之日本社、1961年)では、「茶立場」の名は消え、代わりに「二子山」の名が採用されている。
藤本一美氏は、『比企(外秩父)の山々』(私家版、2018年)において、724㍍独標に対し、「茶立場」(二子山)と表記し、前記の大石氏、奥武蔵研究会の表記を折衷させている。
大石氏は大霧山南の724㍍独標を「茶立場」というのは、地元呼称(里称)とされているが、果たしてどうだろうか。
ところが、私の古い聞き取りノートを再読していると、1987年3月に東秩父村皆谷の旧家・関口家で観音山(中山)について聞き取りをしているとき、たまたまご当主が大霧山に触れ、「大霧山を越えて、粥新田峠から三沢にくだる途中に茶立場という小平地がある」と語っていたのをメモしていたのである。
私としても、当時聞き取りの主眼が観音山だったため、茶立場については単にメモしただけで、それ以上深く聞くこともなく、結局38年間も放置してしまった。
地元・関口家のご当主(当時)から「茶立場は山名ではなく、粥新田峠を越えた三沢側の地名である」という「茶立場は里称」とする大石氏の見解を根底から覆す指摘がなされたのである。
では、どちらが正しいのだろうか。
最近、小川町在住の郷土史家・内田康男氏からお借りした伊豆野輝氏編集の『栗和田風土記』(1977年)のなかに、問題を解く鍵があった。
記述を引用しておこう。
「伝うる処による旧三沢村の上の沢部落の大霧山の裾野に台地があって、茶屋跡といわれる処に昔茶屋があったとか、古老が語っているのは、いつの時代か不明でありますが、たびたび盗賊におそわれたので、ついに引き払ったといわれています」
注目したいのは、「茶立場」と「茶屋跡」、「粥新田峠から三沢にくだる途中の小平地」と「大霧山の裾野の台地」など表現の差はあれ、全体としてみるとおおむね同じような場所を指しているように思われてならない。
つまり、粥新田峠をくだった三沢側の小平地(大霧山裾野の台地)に「茶立場」(茶屋跡)という地名があり、そこに上記のような昔話が残されているとは考えられないだろうか。
最初の関口家で聞いた話だけでなく、こうして栗和田(東秩父村坂本)でも、それに近い昔話が採集されているとなると、「茶立場」(茶屋跡)は粥新田峠道にあり、具体的には東秩父村側からみると、峠を越え、三沢側にくだった最初の小平地ないし台地、さらにいうと上の沢集落にあるという説の有力性が一層高まった。
逆にいうと、大石説(茶立場=大霧山南のピーク名)は誤りという可能性が高い。
では、もっと具体的に茶立場(茶屋跡)があったという台地ないし小平地はどのあたりだろうか。
皆野町三沢から粥新田峠に登る場合、上三沢の広町から三沢川を渡って登り始め、峰の集落を過ぎたあたりに榛名神社がある。
榛名神社は、たしかに広町から粥新田峠に向かうときに登りつめたところにあり、ここからはいったんくだったあと、再度登ると峠につく。
まさに、小平地ないし台地といわれる地形である。
実際に榛名神社の鳥居をくぐった社殿付近には、昔ここに茶店があったと、飯野頼治氏が述べている(飯野頼治『山村と峠道-やまぐに・秩父を巡る』エンタプライズ、1990年)。
要するに、茶立場が山名であるという大石説が誤りである可能性が高くなり、むしろ上三沢と栗和田(坂本)を結ぶ粥新田峠道の三沢側の榛名神社付近という可能性が高まった。
だが以上は私の推測であって、坂本や皆谷、そして峠を越えた上三沢で「茶立場」(茶屋跡)なる地名の調査を行わなければならない。
しかし、結果的には位置が誤ったとはいえ、大石真人氏が今から70年以上も前に「茶立場」という地名を採集してくれたおかげで、このように話を展開することができたのであり、故人(大石氏は2004年に逝去)には感謝したい。
大霧山南のピークの名称を「二子山」とする説についても、もし大石氏が述べておられるように、一片の私設山名表示版に記された勝手な名称であるならば、信憑性はきわめて低いといわざるを得ない。
よって大霧山南の724㍍独標から茶立場、二子山両方の名称を当面消去することにしたい。
つ
つるきり ツルキリ(東秩父村)
秩父郡東秩父村御堂(萩ノ平地区)
第7回「笠山前衛の山々」
2万5千分の1地形図「安戸」
ツルキリ山ともいう。
御堂川(萩平川)と帯沢川にはさまれた尾根(笠山前衛の尾根)上にある。
前記の尾根から少し東に外れたところにある岩峰・リュウゴッパナ(493.8㍍3等三角点:点名「竜ヶ鼻」)の西寄りにある主稜線上の490㍍圏ピーク。
昭文社山と高原地図23『奥武蔵・秩父』(2025年版)では、「ツルキリ山」と表記されているが、萩ノ平では単に「ツルキリ」と呼ばれている。
もともと「ツルキリ」は同峰西側の沢付近の小字名であり、特定の山の名称というより、山の萩ノ平側一帯の総称である。
ともあれ、かつてはツルキリ(山)=リュウゴッパナとされていた。
例えば、大石真人氏は「奥武蔵辞典-山名編-」(『マウンテン・ガイドブック・シリーズ8 奥武蔵』朋文堂、1960年版所収)において、「ツルキリ山 493.8㍍三角点 笠山の北、帯沢の奥にある岩山である。観音山・薬師山などとつなげればハイキングコースができそうである。宛て字、名因とも不明」と記し、明らかにツルキリとリュウゴッパナを同一の山とみなしている。
それが誤りであり、両者が別の山であることが、地元での聞き取りで分かったのは前進である。
大石氏はツルキリの名因を不明としているが、たしかにきわめて珍しい名称である。
私の知る限り、わずかに御坂山塊西部の滝戸山の南西に同名の山があるのみ。
萩ノ平の古老は、昔この辺には雑草のツルが伸び放題になっていて、それを鉈で切りながら進んだから、この地名が付いたというが、山頂南面の深い谷やリュウゴッパナの岩場などから判断し、沢や岩場、断崖などに起因する地形語彙かも知れない。
ツルキリ南の鞍部には、明治38年(1905)9月吉日の銘を刻む馬頭尊が安置されている。
かつて、この地で刈った草を馬で運んでいたところ、道が急峻なため、何頭もの馬が谷に落ちて死んだ。
死んだ馬の霊を慰めるため、萩平の人々がこの地に馬頭尊を建立したという。
て
てらやま 寺山(嵐山町・小川町)
比企郡嵐山町遠山・比企郡小川町下里
第5回「遠ノ平山とその周辺」
2万5千分の1地形図「武蔵小川」
嵐山渓谷を見下ろす好展望の山・大平山(179㍍独標:嵐山町千手堂)から北に延び、やがて南西に方向を変える尾根がある。
この尾根は、「物見山」(214㍍独標)付近から嵐山町・小川町の境界尾根となるが、境界尾根が槻川に落ち込む最後の180㍍圏ピークが「寺山」である。
寺山の名は、古い「菅谷村の沿革」(昭和3年写本、原著作者・年不詳)にも登場している。
「菅谷村の沿革」は寺山について、以下のように記している。
「北に物見山を負い、この山脈があたかも屏風のように連り左右に開いて東は大平山、西は寺山で止っている。南は小倉城址から山脈が東の方に延びて、槻川がその裾を流れている。この山々に囲まれた平坦地は民居や耕地となっている。槻川は平常舟が通じないで、出水の時筏が通るだけである」(『嵐山町史』嵐山町役場、1968年より)
東は大平山、西は寺山、その間に物見山がある「山脈」という表現は、実際の大平山・物見山・寺山の位置関係と見事に符合する。
寺山の南麓には名刹・遠山寺(嵐山町遠山)がある。遠山寺の裏山に当たることから、寺山の名がついたという。
なお現在、物見山」(214㍍独標)には「寒沢山」という誤った山名表示板がある。
さらに、物見山西の四辻(下里観音山[200㍍独標]からの尾根、および西から寒沢山[220㍍圏ピーク]からの尾根がそれぞれ境界尾根に合流する四辻)に「寺山」と書かれた誤った位置の山名表示板がある。要注意。
てんじんやま 天神山(寄居町)
大里郡寄居町富田(上郷地区)
第3回「金勝山とその周辺)」
2万5千分の1地形図「寄居」
鷲丸山(216㍍)を中心とする丘陵をつぶして完成した本田技研(株)埼玉製作所 完成車工場の広大な敷地北にある小丘陵。
180㍍独標を東端とし、その西に「秋葉三尺防跡」のあるピークを連ね、西端が173.8㍍3等三角点(点名「天神山」)のある天神山。
秋葉三尺防跡から天神山にいたる尾根上には、ソフトバンクモバイル、NTTドコモの2つの携帯中継塔が設置され、それに向かう車道が秋葉三尺防跡経由で中継塔まで延びている。
中継塔から天神山までもよく整備された道だが、以前の静けさが失われたのは残念である。
それでも丘陵をたどると、鞍部をへて、3等三角点のある天神山山頂。
小広い山頂には、昭和16年(1941)まで、北山麓の上郷(大字富田)にある「上郷天神社」の社殿が建てられていた。
「上郷天神社の概要」によると、「創建年代は不詳ながら、当地(注:現在の上郷天神社)より南方に聳える天神山に鎮座。富田の上郷地区で祀られていました。明治維新後の神格制定に際し、当社は無格社とされたものの、明治時代後期に実施された神社整理令に際しては、当社が充分な資産を有していたことから小被神社(注:大字富田の鎮守)に合祀されず独立した社として存続したものの、昭和16年に社地天神山が陸軍用地として接収されたことから、当地へ遷座しました」とある。
昭和16年に遷座されるまで社殿のあった山頂には社殿の基石が残されるのみだが、北側の展望が開け、寄居の町並みから北関東の山々などが一望できる。
山頂の西端から200段もの滑りやすい木段を下りると、住宅地に出る。
北に行けば、すぐに里に遷座された「上郷天神社」につく。
てんのうざん 天王山(ときがわ町)」
比企郡ときがわ町別所・日影
第6回「雷電山・御岳山・大峰とその周辺」(今回新事実を加筆)
2万5千分の1地形図「武蔵小川」
雷電山(418.2㍍3等三角点「点名:日影」から明覚方面に延びる長い尾根上にある250㍍独標。
2万5千分の1地形図「武蔵小川」には「堂山」(どうやま)と表記。
堂山は北側の日影(旧玉川村日影)の呼称である。
名称は、台地状の平らな山容によるものであろう。
堂山は、北側山腹(日影側)の小字名でもある。
これに対し、南側の別所(旧都幾川村別所)では、「天王山」(てんのうざん)と呼称している。
別所の鎮守・八剣神社(やつるぎじんじゃ:明神様)は、もともと天王山に祀られていた。
しかし、「氏子の間で生産する口籠が、白い物を嫌う明神様の目に触れてはおそれ多いので、氏子区内を一望できる山上から麓の現在地に降ろしたという。
口籠とは馬の口にはめる道具で、その材料に用いる竹の平を並べて干す様が一面真っ白に見えることを明神様は嫌ったのである。その遷座の年代は伝えていないが、明治の初めまでは祭礼の度に神体の丸石を納めた神輿を天王山まで担ぎ上げていたとの興味深い話が伝えられている」(「埼玉の神社」による)
ただし、「天王山」の山名を、昔山頂に「八剣神社」が祀られていたことから説明することはできない。
「天王山」は「天王様」を祀る神社のある山を指す。
「天王様」は「牛頭天王」(ごずてんのう)を祭神とする神社であり、祇園社、八坂神社、天王社などの神社がある。
明治政府の「神仏分離令」以後、全国の八坂神社や祇園社等は祭神を牛頭天王から素戔嗚尊(すさのおのみこと)に改めているが、人々は親しみを込め、天王様と呼んでいる。
ところが、『新編武蔵風土記稿』比企郡都幾川村大字別所の条では、別所八剣神社の創建年代は不詳としているものの、天正16年(1588)の棟札には経木前司吉信の霊を祀り、加藤隼人宗正が再建したと記されている。
『風土記稿』は、加藤隼人宗正について、源義賢・木曽義仲の家臣団が当地に土着した加藤家の末裔ではないかと記している(ブログ「猫の足あと」埼玉神社案内を参照)。
同社の祭神は日本武尊であり、八剣神社には天王様(牛頭天王)とのつながりは見られない。
とすると、八剣神社が山頂に創建される前から天王山の山名があったのではないか。
それならば、八剣神社以前に山頂に八坂神社(ないし祇園社・天王社)があったのではないか。
それが八剣神社に合祀されたのかどうかなど解明されていない点が多い。
ところで、『武蔵国郡村誌』比企郡都幾川村大字別所の条に以下のような興味深い記述がある、
「東福寺山 高三十丈、周囲不詳、村の東方にあり、嶺上より三分し、東は本郷村、北は日影村、西南は本村に属す。山脈日影雷電山に連なる樹木鬱葱(うっそう)す。南方阿部ノ田より上る七町。山の東を本郷村にて高尾根(たかおね)山という」
同じく『武蔵国郡村誌』比企郡本郷村の条には「高尾根山」に関する記述がある。
「高尾根山 高三十丈五尺、周囲不詳。村の西方にあり、嶺上より三分し、南は別所村、西北は日影村、東は本村に属す。山脈日影村雷電山に連なる。樹木鬱葱(うっそう)登路一条。東方字堅街道より上る六町十二間。山の南を別所村にては高福時山という」
『武蔵通志』にも「高尾根山」に関する説明がある。
「一高福寺山という。高三百五尺。明覚村本郷の西にあり」
さらに、天王山の山頂は別所と日影の境だが、南東山腹(本郷分)には「高尾根」の小字名がある。
以上をまとめると、天王山(別所の呼称)には、日影の呼称である「堂山」以外に、高福寺山(別所の呼称)、高尾根山(本郷の呼称)もあるということになる。
位置的にも、高福寺山は天王山と一致する。
「高尾根」は本郷側の山腹の小字名であり、必ずしも山名とはいえないかも知れないが、逆に本郷側では、西に仰ぐ山を山腹の小字名に因み、高尾根山と呼んでいた可能性も捨て切れない。
ともあれ高福寺山・高尾根山という2つの山名が明治期の2つの地誌に記されていた事実は重い。
今、別所で天王山と言えばすぐに指呼してくれるだろうが、もはや高福寺山の名は人々の記憶から消えている可能性は大であり、もともと「高福寺」が何を指すのか不明である。
最後に、天王山(堂山)山頂には「天王山元旦登山記念」の標柱が立っている。
山麓の別所では、鎮守の八剣神社を麓に遷座したあとも天王山を神聖視し、元旦に登山する習慣が残っているのであろうか。
天王山は、その名の由来をはじめ、別名と推察される高福寺山の山名由来を含め、250㍍の低山ながら謎の多い山である。
てんのみね 天ノ峰(東秩父村・小川町)
秩父郡東秩父村安戸・比企郡小川町勝呂
第2回「官ノ倉西尾根とその周辺」
2万5千分の1地形図「安戸」
官ノ倉西尾根上の烏森山(虚空蔵山)西にある390㍍圏ピーク。
「天ノ峰」は、安戸側の呼称である。
入山川から眺めると、周囲のなかで一際高く聳えているので、この名がついたという。
天ノ峰西側の中腹から鞍部にかけて、この地域には珍しい見事な竹林が広がっている。
ところで、小川町側の勝呂から鎮守の白鳥神社経由の西山林道が十石沢沿いに延びており、
林道終点から天ノ峰まで明瞭な道が踏まれているようだ。
西山林道を使うと、官ノ倉峠まで迂回せずにk、勝呂の吉田家住宅からそのまま天ノ峰に登り、そこから東に烏森山に行くなり、西に愛宕山に行くなり、西尾根の主要な山に容易に行けるようになった。
と
とうげんびら 道元平(ときがわ町)
比企郡ときがわ町田黒
第4回「仙元丘陵」
2万5千分の1地形図「武蔵小川」
「白石」(しろいし)から東に延びる尾根北側の岩場(天狗岩)の上付近の総称。
天狗岩は、埼玉県指定天然記念物「道元平ウラジロ群落」の自生地。
道元平は、標高200㍍ほどの丘陵北面の急崖地(天狗岩を中心とする)からなっている。
斜面は赤松駿およびコナ林によって覆われているが、林のなか暖帯に生育するウラジロ、ツルグミ、ツルアリドウシのほか、温帯のアブラツツジ等がみられる。
このように道元平一帯は、暖帯および温帯に生育しているには植物が共存しており、植物分布上、特徴のある地域となっている。
さらに、これら暖帯性の植物の生育地としては北限に近い。
このような理由で、旧玉川村(現ときがわ町)田黒の道元平約2ヘクタールは、埼玉県により「ときがわ町道元平自然環境保全地域」に指定されている。
道元平こそ、ウラジロ群落が県指定の天然記念物に指定され、それを含む一帯が県自然環境保全地域に指定された結果、玉川スプリングスカントリー倶楽部(現・玉川カントリークラブ)の区域から外れた。
しかし、上流の山や沢がゴルフ場造成により切り土・盛り土されなどの大きな生態系の変化の結果、それが道元平にどのような影響を与えているのだろうか。
それについて果たしてちゃんとした調査がなされているのかどうか不明である。
なお戦前、仙元丘陵が紹介され始めた頃は、八高線明覚駅から道元平・白石に登り、(下里)仙元山・物見山・城山などをへて、(青山)仙元山にいたる「逆コース」が主流だった。
どうだいらさん 堂平山(小川町・ときがわ町・東秩父村)
比企郡小川町腰越、比企郡ときがわ町大野、秩父郡東秩父村白石
第8回「笠山・堂平山」
2万5千分の1地形図「安戸」
比企の名山・笠山から南に籠山のタル(平ノ沢の峠)にくだり、再度登り詰めると、「堂平山」(875.9㍍)山頂につく。
山頂は比企郡小川町腰越、比企郡ときがわ町大野、秩父郡東秩父村白石の境界である。
堂平山の三角点(点名「堂平山」)は、比企・外秩父唯一の1等三角点である。
山頂にある東京天文台(現・国立天文台)の「堂平天文台」は1962年に建設され、1等三角点とともに、堂平山を象徴する存在であった。
堂平天文台は2000年に、当時の比企郡都幾川村に移管され、2005年に新たに都幾川村村営(現・ときがわ町営)の「星と緑の創造センター」の中核施設としてリニューアルされた。
もはや天文台は観測活動を行っていないが、営業期間(12月・1月の冬期休業期間を除く)の毎月第1・第3金曜に「星空観望会」が実施されている。
堂平山頂一帯は、「星と緑の創造センター」として、ときがわ町の一大観光拠点となっている。
センターは、宿泊可能なドーム施設(旧天文台)サイト(山頂)と、林業体験施設・ログハウス・テント・バンガローなどを含むテントサイト(山頂直下)の2つのサイトに分かれ、いずれのサイトにも駐車場が設けられている。
ドームサイトのある山頂は広い芝地の広場で、周囲にはさえぎるものがなく、360度の展望が堪能できる。
堂平山の山名については、山頂から少しくだった平地付近(現・大野共有林)に昔、慈光寺の奥の院があったことから、堂平山と呼ばれるようになったとの説が有力である。
だが、奥の院は鎌倉時代にはなくなっていたという(内田康男『ふるさと腰上-その歴史と伝説-』(1999年)。
ただし、内田氏によると、「2006年、堂平山からは平安時代のものとみられる鉄鉢形土器などが発見され、仏教関係遺跡の可能性が高まってきた。付近の七重集落では、堂平山は慈光寺の奥の院があったと伝えられていて、この鉄鉢によりその可能性が高まったと言える」(内田康男「リリック学院 懐かしき小川町03-⑤「小川町の山々・巨石・名石ーその歴史と伝説-」講座資料、2022年2月19日作成)
もっとも、堂平山の山名由来については、慈光寺の奥の院説のほか、小川盆地から眺められる特有のドーム状の山容に由来するとの説もある。
なお、堂平山は「慈光三山」の一峰である。
慈光三山とは、慈光寺の修験僧が修験の場としていた三山を指す。
三山とは、「與地ノ峰(よちのみね)」(=金嶽・鐘岳)、「遠一山(おんいつさん)」(=堂平山)。「見性山(けんしょうざん)」(=笠山)である。
堂平山へのルートとしては、先の笠山→籠山のタル(平ノ沢の峠)を経由するもののほかに、白石から籠山のタル(平ノ沢の峠)を経由するルート、白石から白石峠、剣ノ峰を経由するルートが知られている。
それらの従来からのルートに加え、都幾川村(現・ときがわ町)が「ときがわトレッキングルコース」として、慈光寺・霊山院から大野の七重集落をへて、山頂の東側にいたるルートを開拓した。
コースの途中で、「七重峠」や「松の木峠」など、ときがわ町が勝手に命名した峠が現われ当惑するが、堂平山から七重、霊山院、慈光寺へ向かうコースが整備されたのは嬉しい限りである。
どうのいりやま 堂ノ入山(寄居町)
大里郡寄居町富田(とみだ)
第14回「四ツ山(四津山)・物見山・堂ノ入山・たかんど」
2万5千分の1地形図「寄居」
2万5千分の1地形図「寄居」の右下を見ると、巨大な本田技研寄居工場(寄居町富田:鷲丸山跡)と、こちらも巨大なワンビシアーカイブズ関東第5センター(寄居町牟礼:物見山跡)にはさまれ、南には2つのゴルフ場(「寄居カントリークラブ」「森林公園ゴルフ倶楽部」)、北は住宅地に囲まれた里山地帯がある。
それが堂ノ入山と「たかんど」(たかんど山)の尾根である。
実は、この2つの山を含む一帯は、寄居町の2つの民間ボランティア団体の手により保全・再生された。
まず、「寄居にトンボ公園を作る会」が寄居町牟礼に「おぶすまトンボの里公園」という名のビオトープを整備した。
その後、「(財)男衾自然公園管理組合」が、雑木とヤブの荒廃した山になっていた堂ノ入山一帯の刈り払いとハイキング道の整備、指導標の設置などを行い、さらに紅山桜と小彼岸桜との交配種であるイギリス生まれの桜アーコレード(和名・男衾桜)を堂ノ入山山頂付近に約千本も植林。
2011年、かつてのヤブ山・堂ノ入山は、「男衾自然公園」の名で寄居有数の桜の名所兼展望ハイキングコースとしてデビューした。
さらに、「男衾自然公園」と「おぶすまトンボの里公園」を結ぶ「たかんど山ハイキングコース」を「寄居にトンボ公園を作る会」が整備中ということで、奇蹟的に残された里山が民間団体(もちろん寄居町も支援しているが)のイニシアティブで保全・再生され、寄居町民をはじめ多くの人々に親しまれているのは嬉しい限りである。
とくに「男衾自然公園」の「男衾桜」は春と秋の二部作。
春には桜祭りも開かれるほか、3月下旬にはカタクリも咲くなど、花一杯の里山に変貌した。
堂ノ入山は、早くも大石真人氏監修の「外秩父概念図」(マウンテン・ガイドブック・シリーズ8『奥武蔵』朋文堂、1954年所収)に「堂ヶ入山」(197㍍)と記載。
大石氏は、前著の1960年全面改訂版(『マウンテン・ガイドブック・シリーズ8 奥武蔵』朋文堂、1960年版)所収の「奥武蔵辞典-山名編-」において、「堂ノ入山(197㍍) 寄居町谷津と牟礼の間にある小山。東上線東武竹沢駅と男衾駅のまん中辺の東側にある」と記している。
標高197㍍とあることから、171㍍の堂ノ入山よりも193㍍のたかんどを指している可能性もあるが、こんな早い時期にヤブ丘陵「堂ヶ入山」の地名採集をされた大石氏の慧眼には感服せざるを得ない。
さかのぼると、『新編武蔵風土記稿』男衾郡富田村内谷津村の条に、「堂之入山 村(富田村)の東の方にあり」との簡単な記述があり、昔から知られた山であったことが分かる。
「男衾自然公園」となった現在、山頂には堂々たる立ち木をバックに立派な山名表示注が建てられ、笠山・堂平山方面の展望が良い。
その他、堂ノ入山周辺には、金比羅宮、仙元大神の両碑が祀られるピークにそれぞれ展望台が設けられ、堂ノ入山以上の360度の眺望を得ることができる。
金比羅宮、仙元大神などの碑が周辺にあることから、堂ノ入山は、古くから地元の信仰を集めた山であったことが想像できる。
さて、堂ノ入山の山名だが、「ドウ」「ド」には、「水量の小さな枝沢が本流に合する」「川の合流点」などの意味がある(岩科小一郎『山村滞在』岳書房、1981年、鏡味味完二・鏡味明克『地名の語源』角川書店、1977年)。
「枝沢が本流に合流」「川の合流点」という語彙を堂ノ入山周辺の地形に当てはめると、見事に符合することが分かる。
堂ノ入山西山麓で、谷津川が新吉野川に合流するのである。
谷津川は新吉野川の支流であり、「枝沢が本流に合する」ことを意味する「ドウ」そのものの地形である。
ここから、堂ノ入山は、「谷津川が新吉野川」に合流する地点付近にある山の意ではないだろうか。
とおのひらやま 遠ノ平山・東野平山・東ノ平山(小川町・嵐山町)
比企郡小川町中爪・下里、比企郡嵐山町志賀
第5回「遠ノ平山とその周辺」
2万5千分の1地形図「武蔵小川」
遠ノ平山は、東を嵐山町志賀(しが・しか)、北を小川町中爪、西から南を小川町下里に囲まれた3つの大字(昔は3つの村)にまたがる山(200㍍独標)である。
それだけに、各大字からは、それぞれ山頂にいたる登路が良く踏まれている。
小広い山頂に御岳信仰の跡を残す低いながらも名山といえる。
交通の便を考えると、武蔵嵐山駅から国道254線を小川町方向に進み、まもなく現れる水坂沼(灌漑用の人工沼)の2つの沼のうち、小川町寄りの上沼の先から取り付く志賀ルートが最も手軽である。
ちなみに、嵐山町志賀は、『新編武蔵風土記稿』比企郡志賀村の項によると、昔は村名を四ヶ村と書いたという。
私の訪れた1989年当時も、地元の古老は志賀を「しか」と発音していた。
上沼からの登り始めこそ明瞭な道も、まもなくヤブっぽい踏跡になる。
だが、灌木の中に放置された「朝日大神」の石碑(裏に志賀講中の銘ががある)が往時の信仰を偲ばせる。
遠ノ平山は2万5千分の1地形図「武蔵小川」でこそ「遠ノ平」の表記だが、『小川町土地宝典』によると、南面のヒラ(下里側)に「東平山」の山字(小字)名がある。
志賀・中爪・下里での聞き取りでは、「とおのひら」の発音は一致していたが、漢字表記となると、「遠ノ平」よりも「東平」「東ノ平」の方が圧倒的だった。
古い地誌をひもとくと、『武蔵国郡村誌』比企郡志賀村の条に「遠平山」、中爪村の条に「東野平山」と記載。
この記載の混乱は『武蔵通志』にも引き継がれ、「遠平山」と「東野平山」をあたかも別の山のように記載している。『通志』では丁寧にも「ヒガシノタヒラ」というルビを振っている。
『武蔵通志』の記載内容は、「遠平山」については、「高さ四百六十尺。志賀の西にあり」とごく簡単だが、「東野平山」となると、「高さ二百五十尺。八和田村中爪の南にあり、東は菅谷村志賀、南は下里村に跨がる。中爪字内洞より上る二町。頂に石碑を建て御岳社遙拝所となす。明治十五年(1882)壬辛新たに之を設け、近村登拝する者多し」と、かなり詳しい。
さらに詳しいのが、明治19年(1886)の「中爪村地誌」である。
「山嶽 東野平山 形状 村中の高山にして扇面を逆建てにしたる形様をます。山脈は左右に分かれ、雀峠・七曲及び日向山等に連る。その他接近の山林起伏し一大山岳をなせり。高 二十五尺。周囲六町三十四間。登路 一条あり。険なり。その程は四町五間。樹林雑樹繁茂せり。景致 頂上に一老松あり。東野平松と号く。その様は一大傘を開しごとく。山中桜ツツジ等多々開花の風景眺望等最も愛すべし。西は遙かに秩父郡諸山と相望む。雑項 明治十五年中、頂上に御嶽神社の石碑を建立す。地方信徒多し。本山名号を里伝にいう日本武尊の東夷征伐の時、当時概征付し後、本山に登賜いて東方を望み、東野平けりと宣いり。号して東野平山名けしといえり」(小川町教育委員会所蔵旧八和田村行政文書336)、山名由来伝説を含め、細かく技術している
『武蔵通志』「中爪村地誌」の記述のとおり、山頂には「御岳山太神 八海山太神 三笠山太神」の巨大な石碑が建っている。
かつて中爪・下里・志賀の三ヶ村で御嶽講が組織されており、三村の境である遠ノ平山(東野平山)山頂に碑を建立した。
現在でも遠ノ平山のことを「御岳山」(おんたけさん)と呼ぶ古老がいる。
なお、明治15年に石碑を建立した頃、山頂に小屋を建て、そこに籠もって太鼓を叩き続けた行者(橋本某)がいたという。
「中爪村地誌」にある「東野平松」かどうかは定かではないが、山頂には立派な男松があり、麓からも一目で分かるほどのものであった。
しかし、落雷で中が空洞になったうえ、数年前にマツクイムシのために枯れてしまった。
現在切り株だけが残されているが、幹回り3㍍ほどの立派な木であったことが想像される。
「トオノヒラ」の山名については、「トオ」「トー」が尾根や山腹を指す山岳語彙であることから、「平らな山頂をもつ山」(山頂が小平地になっている山)とするのが、山頂の形状からみて妥当だと思われる。
「遠ノ平」や「東野平」「東ノ平」「東平」」(人によっては「堂ノ平」)は、「トオノヒラ」への当て字であろう。
山頂から平坦な尾根を西に向かうと、左手に梵字を刻んだ石碑をみて、周囲の展望が開ける(遠ノ平山頂は樹木に覆われ、展望は得られない)。
北側(中爪側)はすぐ近くまで住宅が迫っているが、南側(下里側)は蛇行を描く槻川と周囲の丘陵がぐるりと見渡せる。
ところで、小川町中爪からの登り口にあたるのが、国道254号小川バイパス・中爪橋の下付近から遠ノ平山の北面に突き上げる内洞沢である。
内洞川沢は、典型的な丘陵の谷津地形をなしている。
とくに人工のため池である内洞沼付近は休耕田で荒れ果てていたが、かつて棚田としてコメが生産された土地であった。
この貴重な棚田を復活させるため、現地に住む個人やそれを支援する中爪の有機農業家、市民グループ「遠ノ平山棚田を守る会」などが活動。
数年の努力の結果、十数枚の棚田でコメが生産できるようになり、周辺の環境も整備。
復活した棚田には夏は蛍が舞い、棚田周辺は4月初旬には桜や菜の花が咲き乱れる桃源郷となった。
「遠ノ平山棚田を守る会」の尽力により、遠ノ平山の中爪側登山路(小川町町道)も整備され、志賀側、下里側と合わせ、遠ノ平山への三方の登山路が歩けるようになったことも特筆すべきである。
「内洞沢棚田と蛍の里」へは、遠ノ平山山頂から北に中爪側に下っても行けるし、小川町駅から「パークヒル」行きのバスに乗り、五丁目バス停で降りて直接向かうこともできる。
桜咲く4月初旬に内洞沢の棚田経由で中爪から遠ノ平山に登り、下里側にくだったあと、大聖寺→愛宕山→寒沢山→物見山→寺山→小倉峠→小倉城址→大平山と周回するコースを歩いてみたいものだ。
どうやま 堂山(ときがわ町)
比企郡ときがわ町日影・別所
第6回「雷電山・御岳山・大峰とその周辺」
2万5千分の1地形図「武蔵小川」
雷電山から明覚駅近くの愛宕山まで延々と延びる尾根上にある250㍍独標の旧玉川日影側(北側)の呼称。
堂山北側のかなり広い山腹に、同名(「堂山」)の小字名がある。
堂山の名称は、台地状の平らな山容によるものであろう。
南側のときがわ町別所(旧都幾川村)側では「天王山」(てんのうざん)と呼称している(「天王山」の項を参照)。
どうやまざか 堂山坂(比企郡ときがわ町)
比企郡ときがわ町五明・日影・本郷
第6回「雷電山・御岳山・大峰とその周辺」
2万5千分の1地形図「武蔵小川」
堂山(天王山)東側の鞍部。
ときがわ町日影と五明との境であると同時に、日影・五明の境界からときがわ町本郷へ越える峠である。
現在は、埼玉県道30号飯能寄居線が通る。
ときさん 都幾山(ときがわ町)
比企郡ときがわ町西平
第9回「慈光寺と都幾山・金嶽・士峰山」
2万5千分の1地形図「安戸」
2万5千分の1地形図「安戸」の最新版(2016年2月調製、同年5月1日発行)では、慈光寺裏山(北西)、霊山院北北東側に当たる小川町とときがわ町との境界尾根上の463㍍独標が「都幾山」に当たるかのように見える表記をしている。
昭文社山と高原地図『奥武蔵・秩父』最新版(2024年版)でも、地形図にしたがい463㍍独標を都幾山としている。
しかし、都幾山は慈光寺裏の単独のピーク名であろうか。
否である。
慈光寺の山号が都幾山(都幾山慈光寺)というように、都幾山は特定のピーク名ではなく、慈光寺山域一帯の総称名なのである。
その根拠として、古い地誌をひもといてみよう。
『新編武蔵風土記稿』比企郡平村の条を見ると、「慈光寺」「慈光山」の2つの項目があり、少々戸惑ってしまう。
それでも、慈光寺の解説の最初に「慈光山の上にあり、麓より登ること九丁余なり・・・」とある。
「慈光山」の項目を引用すると、「往古より観音安置の山なれば、慈光の名を得たりしならん。山上よりの眺望殊によくして、東には筑波山を望み、東南は江戸を打越て安房・上総の山々を見渡し、西は秩父ガ岳及び浅間山連り、近く郡内笠山・雲瓦の山々手にも取るべきさまにて、勝景いうばかりなし。山上に与地峯・遠一山など名を得し所あり、及び彼の笠山の内なる見性山を合わせて慈光ノ三山と称すという」と非常に詳しい。
『武蔵風土記稿』の説明から、慈光寺のある山=慈光山=今の都幾山であることが分かる。
そして、与地峯(=與地ノ峰(よちのみね)=金嶽)、遠一山(おんいつさん:堂平山)、見性山(笠山)の三山が「慈光三山」であり、「慈光山」の山上にあるとしている。
慈光山が都幾山と同一であることは、『武蔵国郡村誌』比企郡平村の条からも分かる。
そこでは、都幾山の説明で「都幾山 一名遠一山或いは慈光山と云う」とある。遠一山は堂平山の別名であるから間違っているが、都幾山=慈光山であると明確に述べている
最後に『武蔵通志』の慈光山の説明を見ると、「慈光山 又都幾山遠一山と称す。高一千二十尺。平村西平の北にあり、北は大河村上古寺にまたがる。頂上少平の地を與地峯と云い、其南やや降り観音堂あり。又西に霊山院、東南に慈光寺及釈迦堂あり。登路三條。一は字宿より上る凡九丁。一は日尺より上る十一町。一は上古寺より上る十八町、奈良坂と称し険岨なり・・・」と、非常に情報量豊かである。
慈光山の別名が都幾山であるほか(遠一山は間違い)、頂上が與地ノ峰と呼ばれているということは、都幾山中の一ピークが與地の峰=金嶽ということが分かる。
その他、上古寺からの裏参道である「奈良坂」にも触れており、参考になる。
結論として、繰り返しになるが、都幾山は慈光山ともいい、特定の突起でなく、慈光寺のある山の総称名である。
そして金嶽(與地ノ峰)は都幾山(慈光山)の頂上にある。
そうなると、都幾山の表記は慈光寺のすぐ上にすべきであって、都幾山の最高点である463㍍独標(現在の2万5千図「安戸」、昭文社山と高原地図23『奥武蔵・秩父』で、都幾山と表記している山)を金嶽と表記すべきである。
現在463㍍独標に「都幾山」の私設山名表示板があるというが、これは誤りである。
とやさん 登谷山(東秩父村・皆野町)
秩父郡東秩父村大内沢・秩父郡皆野町三沢
第11回「二本木峠・皇鈴山・登谷山)
2万5千分の1地形図「安戸」「寄居」
皇鈴山からヤセ尾根をくだり、グミの木峠から登り返した668㍍独標。
『武蔵国郡村誌』秩父郡大内沢村は、「登谷山 高八十丈。周回不詳。村の西にあり、嶺上より二分し、東は本村(注:大内沢村)に属し、西は三沢村に属す。村の西より上る十八町五十間。即ち、三沢道なり」と記す。
『武蔵通志』は、「登谷山 高八百尺槻川村大内沢の西にあり」と解説している。
山頂からの展望はそれなりだが(東側の展望は良好)、皇鈴山の大展望には遠く及ばない。
東秩父村大内沢を象徴する名山だが、山頂のマイクロウェーブ中継所が使用を中止した後そのまま放置され、今や廃墟状態。
かえって展望を邪魔し、山頂の雰囲気を害する存在になっていて残念な限りだ。
それでは登谷山の山名は何に由来しているのだろうか。
皇鈴山南の二本木峠には、日本武尊(たまとたけるのみこと)にまつわる伝説がある。
「日本武尊は東夷征伐の折、この峠(=二本木峠)で食事をされた。その時使った杉の箸をさしておいたところ、根がはえて峠名の起こりの二本の大杉になったという。尊は峠より北に連なる稜線を腰に鈴をつけて歩かれた。その鈴の音を聞いた鈴草がいっせいに開花したので、その山は「皇鈴(みすず)山」と呼ばれるようになった。皇鈴山を越えると日が暮れてしまい、次の峰は夜登られたことから、その山は「登夜(とや)山」になったという」(飯野頼治『山村と峠道ー山ぐに・秩父を巡るー』(エンタプライズ、1990年)
だが、この伝説は「登谷山」(登夜山)の漢字表記に付会したものであり、「トヤ山」の発音から推測していくべきだ。
「トヤ」には山の鞍部や山中で鳥をとる人の小屋」などいろいろな意味がある。
大石真人氏は「奥武蔵辞典-山名編-」『マウンテン・ガイドブック・シリーズ8 奥武蔵』朋文堂、1960年版所収)で、「山名はおそらく鳥家(とや)のあった山から出たのであろう」とされているが、これが「鳥家説」の代表的な見解である。
ここでは、やや違った視点から考えてみたい。
もう少し「トヤ」の意味を探ると、「草刈場」の意味もあることが分かった(鏡味完二・鏡味明克『地名の語源』(角川書店、1977年)。
登谷山からグミの木峠の山稜の東側は大内沢共有地であり、江戸時代以降、草地で秣場として利用していた。
その後、杉や檜を植林したが、「草地=秣場」のテッペンにある大内沢の象徴的な山として「トヤサン」の呼称が生まれ、それに「登谷山」の漢字を当てたと考えることができる。
なお、登谷山のことを、大内沢の人々は「雨乞山」とも呼んでいた。
真下通雄氏は、1980年出版の自著のなかで、子供の頃経験した大内沢の雨乞いの模様を再録している。
全文引用すると長いので、簡潔にまとめておこう。
大正12年(1923)の夏の終わりの頃、既に1ヶ月も雨らしい雨がなかった。
農作物の被害は著しく、こんな旱魃は経験したこともないと人々がこぼすようなった。
そこで大内沢でも雨乞いを催すことになり、ある日の午後、昔から雨乞山といわれている登谷山の頂上へ百余人の村人が大太鼓三、小太鼓八個を担いで参集した。
やがて山頂の適当な場所に太鼓が据えられ、八大竜王を呼ぶことになった。
雨乞いの経験のある長老の指導で、彼が先ず音頭をとり、皆さん大声で復唱することになり、大太鼓、小太鼓のたたき方も長老が指導した。
長老が大空に向かい「なーむ、なんだあ、りゅうじんおう」と叫ぶと、大勢が復唱し、間髪を入れずに、小太鼓が、続いて大太鼓が力強く叩かれ、さらに長老が「南無、跋難陀竜神王」と音頭をとると、大勢が復唱し、大小の太鼓を叩く。
八大竜王を呼び終えると、また、これを初めから繰り返し行った。
夕方になって雨乞いが効いたのか、にわかに雲が出てきた。
やがて雲は山頂にまで広がった。
そして、雨乞いの効果てきめんで細かい雨が降ってきたので、雨乞いは夕方5時半頃やめ、皆は下山し、自宅に急いだ。
だが自宅に戻ると雨がやんでしまった。それから3日ほど経ってから大雷雨があり、翌日・翌々日も雷雨になり、ようやくにして十分な雨に恵まれた(真下通雄『銀河縹渺-大内沢の歴史考-』(1980年)
登谷山北西の657.7㍍2等三角点峰の点名は「雨乞山」である。
三角点峰で雨乞いをした記録がないことから、おそらく登谷山の別名である「雨乞山」を何らかの事情で採用したのではなかろうか。
したがって、657.7㍍2等三角点に、三角点の点名をもとに、雨乞山と命名するのは誤りである。
なお、657.7㍍2等三角点峰について、日下部朝一郎氏は『秩父路の峠道』(木馬書館、1981年)33頁の略図において、「ヨロイ山」の名をあてている(説明はない)。
とんびいわ とんび岩(東秩父村)
秩父郡東秩父村大内沢
第11回「二本木峠・皇鈴山・登谷山」
2万5千分の1地形図「安戸」
皇鈴山からグミの木峠へ向かう途中にあるヤセ尾根(金場の平)東側山腹にある巨岩
とんびいわ とんび岩(小川町)
比企郡小川町腰越
初出
2万5千分の1地形図「安戸」
笠山西峰から北に延び、やがて東に方向を変えたあと、帯沢川と館川の間を北西に延びる「笠山郡界尾根」上にある「タカハタ」(高旗山・高畑山:407.6㍍4等三角点)の山腹にある巨岩。
高さ約9.55㍍、周囲約28.3㍍あるという(内田康男「リリック学院 懐かしき小川町03-⑤ 小川町の山々・巨岩・名石-その歴史と伝説-」令和4年2月19日)
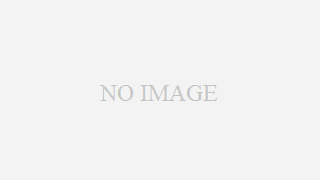

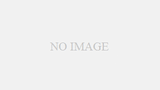
コメント