比企・外秩父の気になる山や峠を手っ取り早く知りたい方のために、「比企・外秩父の山徹底研究」14回のエッセンスに未紹介の山を加えたコンプリートな小辞典をつくってみました。
山名については、なるべく山名の由来を記すことにし、峠名・巨石名のか、重要な地点名も数カ所取り上げました。
「愛宕山」「物見山」など同名の山がいくつもある場合は、標高の高い順に掲載しています。
以、凡例を示しますが、山名・峠名についてもっと詳しく知りたい方は「徹底研究」の該当回を参照してください。
また、各項目をカバーする国土地理院発行2万5千分の1地形図を挙げておきますので、2万5千分の1地形図および昭文社・山と高原地図23『奥武蔵・秩父』(奥武蔵研究会調査執筆)を見ながら読み進めると、良く分かるでしょう。
誤りを発見したり、疑問点があれば、「問い合わせ」を使ってご指摘いただければ幸いです。
今回は完結編の「な~わ行」です。
(凡例)
見出し
かさやま 笠山(小川町・東秩父村)
本文
比企郡小川町腰越・秩父郡東秩父村白石
第8回「笠山・堂平山」(比企外秩父徹底研究の回数)
2万5千分の1地形図「安戸」
説明文
○○○・・・
それでは、比企・外秩父のディープなワールドに浸ってください。
な
なかやま 中山(東秩父村)
秩父郡東秩父村皆谷・御堂
第7回「笠山前衛の山々」
2万5千分の1地形図「安戸」
珪石採石のため消滅した東秩父村皆谷の名峰「観音山」の別名。
詳細は「観音山」(東秩父村)の項を参照。
ななえとうげ(ななえごえ) 七重峠(七重越)(ときがわ町)
比企郡ときがわ町大野
初出
2万5千分の1地形図「安戸」
最近、堂平山から東に延びる小川町とときがわ町の境界尾根を林道栗山線が乗っ越す付近に、ときがわ町は「七重峠休憩所」を設けている。
「七重峠休憩所」は、ときがわ町が整備した「ときがわトレッキングコース」(西平~七重~堂平)の休憩ポイントである。
ときがわトレッキングコースは、慈光寺入口バス停(西平)→霊山院→七重休憩所→七重峠休憩所→森の広場→松の木峠→堂平山を3時間で結ぶ新設のコースである。
問題は「七重峠休憩所」について、ときがわ町が「七重峠休憩所は『七重休憩所』と区別するための便宜的な名称です。『七重峠』はここではなく、堂平山~笠山にあります」とマップに明記していることである。
つまり、トレッキングコース上に、「七重休憩所」と「七重峠休憩所」があり、前者と名称を混同しないように、後者について便宜的に「七重峠休憩所」と命名した。
そして、本当の七重峠は、そこから遙かに離れた笠山・堂平山の鞍部ということである。
しかし、昭文社山と高原地図23『奥武蔵・秩父』(2025年版)では、ときがわ町がトレッキングコース上の「七重峠休憩所」は便宜的な名称であると注意を促しているにもかかわらず、「七重峠休憩所」のある地点を「七重峠」と表記。
ときがわ町が本当の「七重峠」としている笠山・堂平山の鞍部から笠山峠の名を残しながら、もう1つの七重峠(七重越)の名を消してしまった。
従来、笠山・堂平山の鞍部には2つの峠があるとされてきた。
北側が笠山峠で、東秩父村白石と小川町腰上を結ぶ峠。
南側が七重峠(七重越)で、東秩父村白石とときがわ町大野を結ぶ峠とされてきた。
ときがわ町の「ときがわトレッキングコース」マップも、笠山峠・七重峠の区別を踏襲している。
しかし、笠山・堂平山鞍部の「笠山峠」「七重峠」(七重越)は、いずれも先駆者(大石真人氏をはじめとする)が地元呼称と関係なく便宜的に付けた名称がハイカーの間で定着したものである。
『奥武蔵・秩父』を調査執筆した奥武蔵研究会は、七重峠(七重越)を白石側呼称の「籠山のタル」と改めているが、なぜか笠山峠の名は残している。
これも間違いで、白石ではハイカーの言う「笠山峠・七重峠」をひっくるめて「籠山のタル」としているのであり、小川町の腰上では「平ノ沢の峠」と読んでいるのである。
繰り返すが、山と高原地図23『奥武蔵・秩父』から七重峠(七重越え)を消し、籠山のタルとしたのだから、笠山峠も消すべきであり、両者(笠山峠・七重峠)をまとめて、籠山のタル(平ノ沢の峠)とすべきである。
同時に「七重峠休憩所」に七重峠と表記してしまった誤りを訂正すべきである。
に
にのみやさん 二ノ宮山(滑川町)
比企郡滑川町伊古
第13回「大立山・二ノ宮山・高根山」
2万5千分の1地形図「武蔵小川」
滑川町の最高点で、131.7㍍2等三角点(点名「伊古」)。
その優美な山容から、古くから信仰の対象になってきた。
『秩父群村誌』比企郡伊古村の条は、「二の宮山 高さ四十丈、周回二十五町。村の乾の方に孤立す。嶺上に伊古乃速御玉姫の小祠あり。老松数株及び雑樹繁栄し、風景奇絶。字の上より上る七八町」と記す。
『武蔵通志』も、「高さ四百尺。宮前村伊古の西北にあり。頂に伊古乃速御玉姫神社古祠あり。老松数株を存す」と記している。
これらの古い地誌にも書かれているように、滑川町伊古の鎮守であり、比企郡の総社ともいわれる伊古神社(伊古乃速御玉比売神社:いこのはやみためひめじんじゃ)は、当初、二ノ宮山山頂に祀られていたという。
「仁賢天皇の時、蘇我石川宿禰の子孫が当地を開き、君祖三韓征伐の応徳を仰いで、当地二ノ宮山頂に弓箭の祖、安産の祖と崇徳して3柱の神霊を祭ったのに始まると伝えられる」(『角川地名大辞典11 埼玉県』角川書店、1980年)
その後、伊古神社は文明元年(1469)、現在の中伊古に遷座され、二ノ宮山頂の社殿は奥の院とされた。
二ノ宮という山名は、中伊古の伊古神社が一ノ宮、二ノ宮山頂の奥の院が二ノ宮ということに由来するのであろうか。
伊古神社の奥の院(榛名神社を合祀)のある広い山頂は、1989年当時は雑木が邪魔になってしまったが、東方の関東平野方面の展望が得られる。
ただし、「おおむらさきゴルフ倶楽部」に三方から囲まれてしまったのは残念。
2004年12月の藤本一美氏による山行記録によると、「その二ノ宮山へは、南西側参道を巻き気味にゴルフ場柵越しに登れば、あっけなく131.8㍍2等三角点標石のある山頂に達した。芝地の広場の中央に平成6年(1994)完成の鉄骨製展望台(全高23.7㍍、展望台21㍍)が建ち、みんなで登ってみた。標高差153㍍地点からの何のさえぎるもののない360度の大展望があったが、ラフな展望説明板にはちょっと物足りなかった。(中略)眼下のゴルフ場の先には、堂平山、笠山、大霧山を始めとする奥武蔵の山並みが続き、その裏には両神山も現出。登谷山の右手後方には雪雲をかぶった浅間山の白い峰が見え、榛名・赤城山方面の火山群も名称に見えた」(藤本一美『比企(外秩父)の山々』私家版、2018年)
私が最後に登った1989年の5年後に展望台が完成。
『群村誌』が「風景奇絶」と賞賛した展望が戻ったようだ。
だが、眼下のゴルフ場だけはいただけない。
伊古神社の祭神でもある竹内宿禰(すくね)が東国巡視の際に、この山上より村里の状況を視察したといわれる。
山頂の伊古神社奥の院に合祀される榛名神社の例祭は春日待ちといわれ、毎年4月15日に行われる。
当日は滑川町伊古の各地区の氏子総代が山頂に登拝。子どもには団子が配られる。
この日は「ふせぎ」(防ぎ)といって、伊古の各地区(組)では、他地区との境の道の両側にしめ縄を張り、そこにワラジを吊して疫病神が入らないようにした。
団子は、各組ごとに当番(用番)を決めて、当日は用番の家に各戸から米を集めて団子を作り、山上に運び上げた。
また、山頂に八大竜神の碑が祀られていることからも分かるように、二ノ宮山は伊古の雨乞いの山であった。
雨乞いは敗戦直後の頃まで行われていたが、まず伊古神社で、藁でヘビを作って(中に生きたヤマカガシを入れる場合もある)、拝んだあと、滑川の堰(伊古堰)でもむ。
次に、新沼の水でもう一回もんで二ノ宮山に登り、山頂の松に縛り付けて、八大竜神に降雨を祈願したという。
にほんぎとうげ 二本木峠(皆野町・東秩父村)
秩父郡皆野町三沢・秩父郡東秩父村坂本
第11回「二本木峠・皇鈴山・登谷山」
2万5千分の1地形図「安戸」
粥新田峠と登谷山のほぼ中間にある峠。
秩父郡皆野町三沢と秩父郡東秩父村坂本を結ぶ峠である。
現在の峠は、山稜を走る県道三沢坂本線と、峠に登る林道和地場線が合流する車道の一地点に過ぎず、ひなびた峠を想像すると、あまりの落差に驚かれるだろう。
峠の端にたたずむ石積みの上に安置された石宮がわずかに往時の峠の面影を残している程度。
この石宮には「大正七年三沢村玉川耕地一同」の銘が刻まれている。
峠にはヤマツツジが植えられており、5月上旬に一斉に開花するときは見事の一言。
さて、二本木峠にはダイダイボウと日本武尊にまつわる伝説が残されている。
(デイダボウの足跡)
「昔、デイダボウ(デイラボウ・ダイダボウ)という巨人があらわれた。腹が空いたので、笠をぬいでおき、粥新田峠に腰をかけて休んだ。笠をぬいでおいたところが今の笠山である。荒川の水を口にふくみ山に向かってふいたところ霧がかかった。これが今の大霧山である。それから粥を煮て食べた。そこが今の粥新田峠である。また持っていた二本の箸を立てた。これが今の二本木峠である。腰をおろしたところはやすみ石という。デイダボウの足跡は大霧山の頂上や粥新田峠の下にもあるという」(韮塚一三郎編著『埼玉県伝説集成 上・自然編』(北辰図書出版、1973年)
(日本武尊に因む伝説)
「日本武尊は東夷征伐の折、この峠で食事をされた。その時使った杉の箸をさしておいたところ、根がはえて峠名の起こりの二本の大杉になったという。尊は峠より北に連なる稜線を腰に鈴をつけて歩かれた。その鈴の音を聞いた鈴草がいっせいに開花したので、その山は「皇鈴(みすず)山」と呼ばれるようになった。皇鈴山を越えると日が暮れてしまい、次の峰は夜登られたことから、その山は「登夜(とや)山」になったという」(飯野頼治『山村と峠道-山ぐに・秩父を巡るー』(エンタプライズ、1990年)
いずれも、地名の漢字表記に付会した伝説の域を出ない。
『武蔵国郡村誌』秩父郡坂本村の条では、「二本木峠 坂本村の西北にあり、嶺上より二分し、東は本村、西は三沢村に属す。村の東方字内手より上る一里。即ち小鹿野道なり」と記す。
『武蔵通志』でも「二本木嶺 粥新田峠の北にして、西は三沢村に属す。坂本字内手より上る一里。小鹿野に至る支道なり」とほぼ同様の内容を記載している。
いずれの地誌にも書かれているように、二本木峠は、小川町から坂本村に出て、峠から三沢村におり、小鹿野町に向かう古い峠道であった。
なかでも、「和紙の原料コウゾを秩父から小川へ運ぶ峠として賑わっていた」(『角川日本地名大辞典11 埼玉県』角川書店、1980年)
は
はっかいざん 八海山(小川町)
比企郡小川町青山(青山上地区)
第6回「雷電山・御岳山・大峰とその周辺」
2万5千分の1地形図「武蔵小川」
小川町青山・青山上(あおやまかみ)地区の奥(八高線西側)に広がる丘陵を、地元では「福寿山」(ふくじゅさん・ふくじゅやま)と総称している。
福寿山の最高点が「御岳山」(御嶽山)(297㍍独標)である。
御岳山の山頂には、御岳山座生大権現の像と姿・形の同じ石蔵(サイズは小さいが)が祀られている。
江戸時代に木曽御嶽山の王滝口登山道を開山した普寛上人が開山したのが八海山・三笠山であり、御嶽山・八海山・三笠山は御嶽三太神として祀られている。
御嶽信仰が盛んだった小川町でも、中爪と下里、志賀の境にある遠ノ平山(東野平山)では、御嶽三太神一体の石碑が山頂に祀られている。
これに対し、青山の御岳山では、青山上からの参道にあたる2つの山をそれぞれ八海山、三笠山と呼び、それぞれの山頂に「八海山様」「三笠山様」の石像が、八海山の北肩には「半蔵坊霊神」が祀られていた。
八海山は、御岳山北東の260㍍圏の平頂稜で、その南の289㍍独標(ゴルフ場造成前の2万5千分の1地形図「武蔵小川」では、大峰山と表記)が三笠山である。
八海山、三笠山は南の大峰(ときがわ町小北)とは尾根続きであり、御岳山・八海山・三笠山・富士見平・大峰一帯は、かつて秣場で、草地に灌木が混じる好展望の丘陵であった。
残念ながら、八海山・三笠山・富士見平は「(仮称)武蔵台カントリークラブ」(現・アドニス小川カントリー倶楽部)の造成により消滅し、八海山様の石像は御岳山頂に遷座された。
はなやま 花山(寄居町)
大里町寄居町風布
第13回「釜伏峠・葉原峠・大平山・金ヶ嶽・金尾山」
2万5千分の1地形図「寄居」
釜山神社の奥宮がある釜伏山(男釜)から北に岩稜をくだると、日本水入口(日本水は現在立ち入り禁止)。
さらに相変わらずの岩尾根を約10分ほど進むと、「花山」(はなやま)につく。
埼玉県の天然記念物に指定されている「ゴヨウツツジ」(アカヤシオ・シロヤシオ)自生地で、開花期には、岩場にアカヤシオのピンクの花が、それに少し遅れシロヤシオの白い花が栄え、実に美しい光景だった(1985年の訪問時)。
山頂中央に、「埼玉県指定天然記念物ゴヨウツツジ自生地」と書かれた昭和40年(1965)10月建立の石碑があり、もう一つの古い石碑(大正13年(1924年)3月の銘)には「釜伏山名物花山」と刻まれている。
はばらとうげ 葉原峠(長瀞町・寄居町)
秩父郡長瀞町井戸・大里郡寄居町風布
第13回「釜伏峠・葉原峠・大平山・金ヶ嶽・金尾山」
2万5千分の1地形図「寄居」
釜伏峠から延びる外秩父主稜線が塞ノ神峠、仙元峠(浅間峠)をへて達する峠。
南の505㍍独標と北の大平山(538.6㍍3等三角点峰)とのちょうど中間の鞍部にある峠。
寄居側の風布から来た林道が峠を越え、長瀞側の井戸へ乗っ越している。
峠には古い石の道標があり、「左小林、右扇沢、植平、左井戸、右風布」と刻まれている。
名前からは、草原の明るく開けた峠を想像するが、1985年(約40年前)に訪れたときには、明るく開けた仙元峠とは対照的に植林と雑木に覆われ、山稜が迫っているせいか、暗く感じられる峠だった。
今はどうだろうか。
葉原峠は、この山稜では釜伏峠に次いで有名な峠で、古い地誌にもその名が見える。
『新編武蔵風土記稿』秩父郡井戸村の条では、「葉原峠 村(井戸村)の東にあり、隣村風布村へ越ゆる峠にして、登ること十五六町ばかり。山上にて風布村と界限せり」と記す。
『武蔵国郡村誌』秩父郡井戸村の条では、「葉原峠 (中略)高さ七十五丈。村(井戸村)の東にあり。嶺上より三分し、東は風布村に属し、西は本村に属し、北は岩田村に属す。村の北方より上る三十五町険岨」と記述されている。
さらに『武蔵通志』には、「葉原山 高さ七百五十尺。白鳥村井戸の東北にあり。風布岩田にまたがる」と記している。
葉原峠から長瀞側の岩根神社に向かってくだると、1985年当時は進行方向右に一軒家があった、
この家が通称「テッペン金サン」と呼ばれる家である。金さんは村の一番高いところに住んでいるので、近所の人々はそう呼んでいるという。
果たして、40年後の今、家は残っているのだろうか。
もう少しくだった岩根神社(大字井戸)はツツジ群落で有名。
「岩根神社の境内、社務所前の山林一帯、参道の両側に樹齢百年を越す見事なツツジが千株もの大群落をつくり、 満開の時には全山花で埋まり壮観を呈する。
4月17日の春祭のころが満開で、巨木となったツツジのトンネル、境内からの眺望などの素晴らしさは、関東でも例を見ないほどである」(長瀞町教育委員会・長瀞町文化財審議委員会『長瀞ひとり歩きー文化財・名所を訪ねてー』長瀞町教育委員会、1984年)
再度葉原峠に戻り、反対側の寄居町風布方面にくだると、大字風布の小林地区に出る。ここは、みかんの北限で、みかん畑が一杯に広がる。
長瀞側・寄居側の風布が白鳥村のもと一体だった頃(1889~1943)、分教場の小学課程を終えた学童たちが、井戸(現在の長瀞町井戸)の白鳥尋常小学校の高等科に通った道が葉原峠道でもあった。
葉原峠には悲しい歴史もある。
葉原峠を寄居側にくだった小林地区は秩父困民党のなかでも一番勇猛であった風布組の人々が小林の金比羅山に集まり、夜になり、葉原峠を越えて吉田町の椋神社の本隊と合流した(明治17年10月31日)。
これが秩父事件の勃発である。
風布組は「団結力が強く、終始先頭に立って戦ったので犠牲者も多く出たという」(飯野頼治『山村と峠道―山ぐに・秩父を巡る』(エンタプライズ、1990年)
ひ
ひとついわ 一ツ岩(小川町)
比企郡小川町木部
第2回「官ノ倉西尾根とその周辺」
2万5千分の1地形図「安戸」
官ノ倉山の北を流れる木部川は、天王沼の先で不動入(本流)とイラ沢に分かれる。
イラ沢は官ノ倉峠に登るハイキングコースに沿っているが、不動入(上流にある「北向不動」に由来)はさらに右俣の本流と左俣の「ウス入」に分かれる。
ウス入をつめると、山林のなかに高さ数十㍍もの大岩にぶつかる。これが「一ツ岩」である。
「一ツ岩」から急な山腹を登ると、官ノ倉西尾根に出る。
西尾根に出て、少し西に進んだところが、官ノ倉峠と烏森山とのほぼ中間地点。
この地点に、安戸の方が祀ったという山ノ神の小祠がある。
ひのきだいら 檜平(東秩父村・皆野町)
秩父郡東秩父村皆谷・秩父郡皆野町三沢
第10回「新定峰峠・旧定峰峠・大霧山・粥新田峠」
2万5千分の1地形図「安戸」
旧定峰峠から北に大霧山に向け、最初に登り詰めた700㍍圏ピーク。
西に大きな支尾根が分かれる。
このピークについて、奥武蔵研究会著『ブルーガイドブックス4 奥武蔵と比企丘陵』(実業之日本社、1961年)では、「桧平」(ひのきだいら)と表記。
寺田政晴『アルペンガイド17 奥多摩・奥武蔵』(山と渓谷社、1983年)でも、「桧平(ひのきだいら)と呼ばれる小広いピーク」と記している。
ただし、同じ奥武蔵研究会調査執筆の昭文社山と高原地図23『奥武蔵・秩父』(2025年版)には「桧平」「檜平」の記載は無い。
しかし、ヤマレコ、YAMAPなどの山行報告、その他のネットの山行記録には「檜平」の名が頻出するので、現在、現地に「檜平」の名を記した公設の山名表示板が設置されている可能性がある。
今後、地元である東秩父村皆谷や白石を中心に、秩父市側の定峰などで呼称の確認を行う必要があるだろう。
ひばらとうげ 碑原峠(小川町・ときがわ町)
比企郡小川町腰越・比企郡ときがわ町大野
初出
2万5千分の1地形図「安戸」
小川町腰越の最奥の集落「赤木」から館川の上流・梅沢ヤツに沿って、ときがわ町大野の七重集落に越える峠。
現在は林道が通っている。
この峠名について、大石真人氏が「外秩父概念図」(『マウンテン・ガイドブック・シリーズ8 奥武蔵』朋文堂、1954年版所収)で「碑原峠」(ひばらとうげ)と表記して以来、この名称がハイカーの間で定着してきた。
大石氏は『マウンテン・ガイドブック・シリーズ8 奥武蔵』(朋文堂、1960年)所収の「奥武蔵辞典-山名編-」においても、「碑原峠(420㍍)都幾村(注:都幾川村が正しい)七重から小川町赤木へこえる峠。字にこう書くが、名因は檜原であろう」としている。
しかし、「碑原」(ひばら)は七重地区のあるときがわ町大字大野の小字名ではなく、大字西平の小字名である。
場所は、小川町とときがわ町との境界上の593.4㍍3等三角点峰(風早山・平萱の三角点)付近(南のときがわ町側)の小字名「風早」のさらに南側の小字名が「碑原」である。「脾原峠」から直線距離で500㍍以上も離れており、赤木から七重に越える峠名とするのは無理がある。
実際、赤木、七重両集落で峠名の聞き取りを行ったが、両集落とも峠名は無名であった。
結論として、脾原峠なる峠名は、地元呼称ではなく、大石氏をはじめとする先駆者がたまたま採集した小字名を峠名としてしまった誤称であろう。
実際、奥武蔵研究会長蛇執筆の昭文社山と高原地図23『奥武蔵・秩父』では、「碑原峠」の名称は消えている。
ふ
ふくじゅさん、ふくじゅやま 福寿山(小川町)
比企郡小川町青山(青山上地区)
第6回「雷電山・御岳山・大峰とその周辺」
2万5千分の1地形図「武蔵小川」
福寿山という場合、「狭義」と「広義」の2つの範囲がある。
「狭義」の福寿山は、小川町大字青山の小字「福寿」にある山の意味である。
具体的には御岳山(297㍍独標)と、その前衛である三笠山周辺を指す。
これに対し、「広義」の福寿山は、青山の南にあり、南端は旧玉川村(現・ときがわ町)日大字日影となる八高線西側の丘陵一帯の総称名である。
「広義」の福寿山が御岳山を含むことはいうまでもない。
地元・青山では、福寿山については、広義の意味で呼称しているようだ。
さらに、古い地誌で「福寿山」という場合も、広義の意味で使っている。
例えば、『武蔵国郡村誌』(明治8年調査)比企郡青山村の条では、「福寿山 村の南にあり、東西百五十間、南北二百間」とある。
『武蔵通志』(明治24~25年)はさらに詳しく、「大河村青山の南にあり、山頂円形にして御嶽神社あり、松檜の間、ツツジ多し」と記す。
両者の記事から、「広義の福寿山」を説明していることは明白である。
さらに『通志』は、福寿山に御嶽神社があると述べ、御岳山が福寿山に含まれるとしている。
もっと詳しく「広義の福寿山」について述べているのが、明治19「青山村地誌」(小川町教育委員会所蔵旧大河村行政文書2)である。
そこでは、「福寿山 中央円形にして、突出し、四囲小丘陵羅列す。景致 ツツジ満山松柏疎々風景絶佳なり。雑項 頂上に松下に御嶽神社の石像あり。ツツジ満開の候は風流才子観山の徒山上群をなす。里俗物見山と称するは則ちこの処なり」と、実に詳しく記している。
福寿山の頂上に御嶽神社の石像があるということは、福寿山の最高点が御岳山(297㍍独標)であるということを意味している。
その周囲に小丘陵羅列す」という表現も、御岳山の周囲に「三笠山」「八海山」などの前衛の丘陵があるというかつての丘陵の姿を彷彿とさせる。
「ツツジ満山松柏疎々風景絶佳なり」という描写も、ツツジこそ見ることはできなかったが、かつての秣場の名残を残す草原に灌木が混じり、小川町方面の展望はもちろん、「富士見平」の小字名が表すように、富士山を望むことができたという地元の古老の話と一致する。
御岳山こそが福寿山と総称される丘陵の最高点(頂上)であり、地元の人々は「物見山」と呼んでいたというのは初耳だが、この一帯ではもっとも標高が高く、1980年代当時、北側の展望が開けていた御岳山に、昔、物見櫓が築かれていたとしても何の不思議はない。
これまでの記述から、広義の福寿山についてまとめると、青山の南(八高線の西側)にあり、南端が旧玉川村日影の丘陵の総称が福寿山。
福寿山の最高点(頂上)が御岳山で、その周囲には八海山、三笠山などの小山がある。
三笠山(ゴルフ場造成前の2万5千分の1地形図「武蔵小川」では、大峰山と表記されていた289㍍独標)の南にあり、旧玉川村境界まで続く草原「富士見平」(小字名でもある)を含め、眺望の良い草原(灌木を含む)であったということである。
「八海山」の項目でも書いたが、八海山・三笠山・富士見平へと続く尾根は、旧玉川村との境界を越えると「大峰」となる。
つまり、福寿山と大峰とは尾根続きであり、大峰(現在の2万5千分の1地形図「武蔵小川」で大峰山の表示がある293㍍独標を含む旧玉川村日影の丘陵一帯の総称。こちらもかつては秣場であった)は福寿山の旧玉川村日影分の総称である。
福寿山を小川町青山奥(八高線西側)の丘陵総称名であるという認識は、1940年代以降この山域を紹介していた先駆者の一致した見解でもあった。
例えば、神山弘氏は『ハイキング』119号(1943年)で、「地図に日影-青山の破線路の通る峠を中心とする丘陵の総称は、福寿山である」と記している。
大石真人氏も、「奥武蔵辞典-山名編-」(『マウンテン・ガイドブック・シリーズ8 奥武蔵』朋文堂、1960年版所収)のなかで、「福寿山(ふくじゅさん)(290㍍)明覚駅から小川町駅にいたる、八高線を中にして仙元丘陵と相対する山一帯をいう」と解説されている。
神山氏・大石氏の説明は福寿山を広義の意味で使っているという点で、おおむね妥当な内容だが、肝心の御岳山について一言も触れていない。
大石氏の「奥武蔵辞典-山名編-」には御岳山の項目さえない。
このような認識が、大石氏の影響が色濃く表れた奥武蔵研究会調査執筆の昭文社山と高原地図『奥武蔵・秩父』に反映された。
1980年代半ば頃までの『奥武蔵・秩父』には御岳山・大峰の表記はなく、福寿山の表記しかなかった。
その後、2万5千分の1地形図「武蔵小川」で289㍍独標(本当は,三笠山)に大峰山の名が記載され、御岳山が「発見」されると、『奥武蔵・秩父』から福寿山の名は消え、御岳山が297㍍独標名に、大峰山が289㍍独標名として記載された。
『奥武蔵・秩父』(2025年版)では、2万5千分の1地形図「武蔵小川」の変更にともない、小川町・ときがわ町境界の293㍍独標に大峰山の表記をしているが、「大峰山」ではなく、「大峰」であり、293㍍独標だけでなく、それを含む小北地区(大字日影)の北側一帯の山の総称名であるということは、「大峰」の項目で触れたとおりである。
福寿山は御岳山・三笠山・八海山・八坂神社・サネ山の奥ノ院など信仰に彩られ、とくに八海山・三笠山・富士見平から日影分の大峰へと続く山稜は明るい草原で、眺望にも恵まれていたという点で、仙元丘陵に匹敵する素晴らしい丘陵であった。
雷電山~大日山(お大日様)~行風山~行風峠~御岳山の尾根も、今とは違い1980年代は、多少のヤブや踏跡の不明瞭な部分はあったとはいえ、スムーズに歩ける縦走路だった。
しかし、大成建設による「(仮称)武蔵台カントリークラブ」(現・アドニス小川カントリー倶楽部)造成により、福寿山は御岳山と八坂神社を除き、すべて破壊されてしまった。
もちろん、三笠山(289㍍独標)・八海山は消滅した。
今さら地図に「福寿山」の名を復活させようにも、そこには変わり果てたゴルフ場しかないというのは、かつての福寿山の姿を知る者にとって悲しい限りである。
開発を免れた尾根続きの大峰が残ったというだけでも、幸いというべきだろうか。
しかし、大峰もすっかり荒れ果ててしまい、かつて山頂部分が草原だった面影は全くない。
最後になるが、「福寿山」(ふくじゅさん)は、神仏習合時代の御嶽神社の本尊「御嶽山座生大権現」の山号であった(=福寿山御嶽山座生大権現)。
ふじみだいら 富士見平(小川町)
比企郡小川町青山
第6回「雷電山・御岳山・大峰とその周辺」
2万5千分の1地形図「武蔵小川」
「富士見平」は小川町大字青山の小字名であり、小字「福寿」の南に当たり、「富士見平」の南は旧玉川村(現・ときがわ町)日影の「大峰」である。
「福寿山」(前項を参照)を広い意味で考えると、大字青山の南にある御岳山を最高点とする八高線西側一帯の丘陵の総称である。
その福寿山の最南端にあるのが、富士見平である。
御岳山前衛の「八海山」「三笠山」(ゴルフ場造成前の2万5千分の1地形図「武蔵小川」で大峰山と表記された289㍍独標)から「富士見平」、そして旧玉川村日影分の大峰は尾根続きであり、かつての秣場の面影を残す灌木混じりの草原であった。
なかでも富士見平は茅戸の草原で、天気の良い日は富士山も眺望できたことから、この名がついたという。
残炎ながら、富士見平はゴルフ場(仮称・武蔵台カントリークラブ→現・アドニス小川カントリー倶楽部)造成により破壊されてしまった。
ふじやま 富士山(小川町)
比企郡小川町高谷・角山
初出
2万5千分の1地形図「武蔵小川」
小川町駅北口から至近距離にある182.1㍍3等三角点峰(点名「高谷」)。
山頂は大字高谷分だが、大字角山と境を接する。
大石真人氏は「奥武蔵辞典-山名編-」(『マウンテン・ガイドブック・シリーズ8 奥武蔵』朋文堂、1960年版所収)において、「東上線小川町駅真北の山。戦時中は高射砲陣地が設けられて登山禁止となっていた」と述べている。
現在は高射砲の代わりに電波塔が山頂を占拠していて、その囲いの外側に「富士浅間大菩薩」と刻まれた石碑が祀られている。
ただし、高谷・角山を中心に古くから冨士浅間信仰の山として親しまれていたことは、古い文献から読み取れる。
内田康男氏からご教示いただいた万治2年(1659)5月「角山村大塚村秣場取極絵図」に「富士山」とある。
内田氏の講座資料によると、「『天保巡見日記 亨』国立公文書館所蔵に『天保9年(1838)三月廿六日)高見・能升二村を過て山合谷道に入り高谷村にいたる。この村に高谷富士といえる山あり、眺望絶妙なりと聞ゆへに、村人に案内させて登り見るに、凡十丁余も登り漸頂に至る。松四五本ありて下には蕨を生し、又かたくり・あおばらん杯夥ありて、いつれも花をひらき、四方之眺望言葉に尽かたし、則矢立取出て二図を写すといえとも遠き秩父の峰々はうす霞みをふくみ、近き山々松の梢には桜の咲盛りて、去年の雪の消え残るや、また霰の集りしかと疑れぬ。挿図は、『高野村富士山上より秩父諸山眺望之景』」としている(リリック学院 静かなる小川町03~⑤小川町の山々・巨石・名石-その歴史と伝説』(令和4年2月19日講座資料より)
明治19年の「高谷村地誌」は富士山について、以下のように記している。
「山嶽 富士山 所在 本村(注:高谷村)西南字芹ヶ澤。形状 其形状不二山に似たるを以て、その名称を附せり、山頂平坦にして緑樹繁茂し山脈左左右に分れて村中諸山に連る。高 三拾五丈。周回 拾五町三十間。登路 一條あり。本山ノ東北麓より登る甚険なり。その程五町拾三間。樹木雑樹繁茂せり。景致 頂に浅間神社あり、松樹繁茂し、眺望は山下一目すれば小川の市街、次て槻川流水を望む等その景甚美なり、遙に秩父諸山と相望む。本山及近接の諸山桜多く、花時の風景も美なり」
ふるてらとりであと 古寺砦跡(小川町)
比企郡小川町上古寺
第6回「雷電山・御岳山・大峰とその周辺」
2万5千分の1地形図「安戸」
小川町上古寺とときがわ町雲河原との境で、県道273号線西平小川線が通る「松郷峠」。
小川町側の上古寺から松郷峠に向かう県道の西側に無残な姿を見せているのが光兆産業(株)古寺砕石工場。
この砕石工場により削られ、消え去ってしまった山が「古寺砦跡」。
古くは「城山」とも呼ばれていた山だが、1988年に採掘前の発掘調査が行われた。
それによると、慈光寺裏街道を見下ろす山頂部に小規模な郭(くるわ)を2つ南北に並べ、南の郭先の尾根の先端に掘切があり、北の郭には「のろし台」とみられる焚火土壌が発見された。
きわめて単純なつくりで、急ごしらえでつくった砦であることは歴然であった。
小田原の後北条氏は、天文15~20年(1546~1551)にかけて、当時勢力を誇っていた慈光寺を攻略した。
この慈光寺攻略は、後北条氏の重臣であった松山城主・上田能登守朝直(暗礫斎)により行われ、慈光寺は重要文化財の開山塔が被害に遭うなど深刻な打撃を受け、勢力を失った。
以上から、古寺砦跡は上田氏の慈光寺攻略の最前線の砦として急造されたと考えられる。
そして、天正15年(1590)の豊臣秀吉による小田原城攻略の際、上田氏の居城・松山城も落城。
出城の古寺砦も機能を失い、荒廃したのであろう(梅沢太久夫『埼玉の城-270城の歴史と縄張-(改訂版)』まつやま書房、2023年)。
また、内田康男氏は古寺砦とその北方の腰越錠(城山)を結ぶ間道の存在を確認し、古寺砦は腰越錠の出城的性格をもっていたのではないかと推測している。
2つの城を結ぶ間道は、上古寺の東光寺付近から雷電山~士峰山の尾根(峠)を越え、腰越の矢岸にいたっている。
この峠の入口に「木の城」という屋号をもつ吉田家がある。
昔、古寺砦から腰越城への移動は昼を避け、夜のみであったという。
暗闇では歩行が困難なので、いつも使者は吉田家でかはり火をもらい、無地に腰越城にたどりつくことができたという。
この功績により、吉田家は古寺砦の主から「木の城」の屋号をいただいたという。
腰越城は松山城主・上田氏の慈光寺攻めにあたって最前線をなしており、腰越城主・山田氏は松山城主・上田氏の重臣であった。
こうした関係からも、松山城→腰越城→古寺砦という命令系統で慈光寺攻略を行ったと考えられる。
そして、腰越城とその出城である古寺砦との間には頻繁な往来があったと想像できる(氷川の里上古寺編集委員会『氷川の里 上古寺』氷川神社、1985年)。
松山城主・上田氏の慈光寺攻めの北側の拠点が「古寺砦」であったとするなら、南方の最前線は、ときがわ町西平字大築の「大築城」であった。
ほ
ほそくぼやま 細窪山(小川町・東秩父村)
比企郡小川町木呂子・秩父郡東秩父村奥沢
第2回「官ノ倉西尾根とその周辺」
2万5千分の1地形図「安戸」
官ノ倉西尾根はもちろん、官ノ倉丘陵全体の最高点である421.2㍍3等三角点峰(点名は「奥沢」。
「細窪山」は北東側の小川町木呂子における呼称。
山頂北東側(木呂子側)の小字名「細窪」にもとづく山名である。
細窪山は小川町木呂子と東秩父村奥沢の境界にあるので、奥沢で山名を聞き取りしたが、おおむね無名で、一部の人が「三角点」と呼んでいた。
そのため、小川町側、東秩父村双方の呼称を尊重すると「細窪山」(三角点)と表記するのが正解ということになる。
しかし、この山は長年、ハイカーの間で「臼入り」あるいは「臼入山」なる誤った名称で呼ばれていた。
今でも山頂には「臼入り」「臼入山」などと書かれた私設の山名表示板が、「細窪山」の山名表示板に混じって建てられていて、ヤマレコやYMMAP等ネットの山行記録でも、「臼入り」あるいは「細窪山(臼入山)」などと表記する人が多い。
では、なぜ「臼入り」「臼入山」なる誤った山名が約80年以上にわたってハイカーの間で使われてきたのだろうか。
それを説明する前に、まず「臼入り」について解説しよう。
「臼入り」は正確に書くと「ウス入」である。
「ウス入」は、木部川の支流で、天王池の先で本流(不動入と名を変える)から分かれ、南西に官ノ倉西尾根に突き上げる沢である。
それと同時に、「ウス入」は沢の名称であるとともに、沢の周辺から官ノ倉西尾根にかけての山腹の小字名である。
木部川の上流である不動入(木部の北向不動が沢に沿ってあることからこの名がついた)は「烏森山」に突き上げている。
烏森山は、細窪山よりもかなり官ノ倉峠に寄っており、烏森山と細窪山の間には、天ノ峰、愛宕山などの山々がある。
ウス入は「一ツ岩」を越え、西尾根上に突き上げるが、その突き上げた地点から少し西に寄った地点に山ノ神の小祠がある。
2万5千分の1地形図「安戸」をみても、ウス入が官ノ倉西尾根上の烏森山の東にある366㍍独標のさらに東に突き上げていることが良く分かる。
この地点は、細窪山とは直線距離で1.5キロも離れており、ウス入を421.2㍍三角点の山名とするのには無理がある。
この時点で、既に421.2㍍三角点を「臼入り」「臼入山」と呼ぶことは破綻している。
では、どのような経緯で、誤った山名がついてしまったのだろうか。
詳しくは、「比企・外秩父の山徹底研究」第2回「官ノ倉西尾根とその周辺」の「細窪山」の項で書いたので、ここでは要約にとどめたい。
官ノ倉西尾根を最初にハイキング雑誌に紹介したのが岩満重孝氏と岩崎京二郎氏であり、ともに1941年であった。
両氏の記事では、ウスイリ(岩満氏)、臼入り(岩崎氏)などと呼んでいるが、いずれも沢名・小字名ではなく、西尾根上のピーク名として用いている。
だが、それは421.2㍍三角点峰ではなく、それと官ノ倉峠の間にあるピーク(正確な場所は不明)として使っており、アバウトな位置としては、ウス入のツメに使い山を指している。
おそらく両者は地元(小川町木部)で小字名である「ウス入」を採集し、それを特定のピークの名称として転用したのではないだろうか。
ところが、その後、新ハイキングペンクラブ著『新しき山の旅』(昭和17年、昭和書房)所収の坂倉登喜子氏(岩根登喜子名)執筆の「官ノ倉山、小瀬田越え」で、事態は一変した。
上記の記事では、略図に三角点は記載されていないが、ガイド文では官ノ倉山に登ったあと、再び官ノ倉峠に戻り、西尾根を「臼入山」までたどっている。
そして、文中に「臼入山からは、北へ八王子を経て、中郷部落へ降るなり、或は奥沢へ降ってバスに乗るなり」とあるように、ここでは「臼入山」は明らかに3等三角点峰と同一視されている。
この坂倉氏の誤りを大石真人氏も踏襲。
大石氏監修の「外秩父概念図」(『マウンテン・ガイドブック・シリーズ8 奥武蔵』朋文堂、1954年版所収」)では、421.2㍍三角点に「臼入り」と表記。
1960年版の『マウンテン・ガイドブック・シリーズ8 奥武蔵』(朋文堂)所収の「奥武蔵辞典-山名編-」でも、「臼入り頭」とし、「官ノ倉丘陵中の最高峰。官ノ倉峠から不動入頭をへて細経が尾根上にあるが、夏秋にはかなりヤブがわずらわしい」と記している。
坂倉氏・大石氏の影響下にあった奥武蔵研究会(大石氏は同会2代目の代表、坂倉氏は三代目の代表)が昭文社山と高原地図『奥武蔵・秩父』で、両氏の誤りをそのまま踏襲し、421.2㍍三角点峰に長年「臼入り」と表記し続けたことは当然の成り行きであった。
現在でこそ、同会も誤りを訂正し、細窪山と表記するとともに、「誤った臼入山の標識あり」と注記している。
それでも、同じ昭文社発行の「都市地図 埼玉県12 東松山市 小川・嵐山・滑川・吉見町 ときがわ町 東秩父村」では、相変わらず421.2㍍三角点峰を「臼入山」としている。
おそらく421.2㍍三角点峰をめぐる山名の混乱は今後も続くだろう
最後に、三角点から奥沢にくだる途中にある石尊様(2万5千分の1地形図「安戸」で421.2メートル3等三角点から南に延びる尾根途中の神社記号。奥沢から石尊様まで破線路が記入されている)についても簡単に言及したい。
阿夫利神社(石尊様)の例祭は以前、4月12日に行われ、奥沢の集落総出で登拝した。
しかし、その例祭も久しく行われておらず、社殿もすっかり傷んでしまった。
ぽんぽんやま ポンポン山(熊谷市)
熊谷市小江川
第13回「大立山・二ノ宮山・高根山」
2万5千分の1地形図「三ヶ尻」
滑川町福田の高根山(105.1㍍3等三角点)北西にある小山。
こちらは熊谷市小江川(おえがわ)(合併前は、大里郡江南町小江川)で、山頂にはコンクリート製の高区配水池が占拠している。
その上に鉄骨の小展望台がある。
高根山は「四顧爽潤」という『武蔵通志』の過去の表現に反し、樹林に覆われ、山頂からの眺望はゼロ。
それを補って余りあるのがポンポン山の小展望台からの大展望。
北に山が何もなく、関東平野に直接面する丘陵というだけあって、関東北部の山々の眺望をはじめ、360度のワイドな展望が素晴らしい。
100メートルに満たない標高を忘れるひとときだ。
ポンポン山というと、吉見丘陵の玉鉾山(たまぼこやま)が有名だが、ここ小江川のポンポン山は玉鉾山と違って山頂の地面を踏んでもポンポンと音がするわけではない。
山頂直下に開口1.5㍍、奥行2㍍ほどの横穴が存在する。
これは古墳時代の高根横穴群のひとつと考えられているが、この穴で手を叩いたり、足を踏みならすとポンポンという反響音がすることから、ポンポン山の名がついた。
横穴の奥壁に観音像が埋め込んであったとは、小江川の古老の話。
ぽんぽんやま ポンポン山(吉見町)
比企郡吉見町田甲(たこう)
初出
2万5千分の1地形図「東松山」
比企丘陵の東端にあたる吉見丘陵の末端にある。
大字田甲の鎮守・高負比古根(たかおひこね)の域内裏に標高38㍍の小さな岩山がある。
これがポンポン山である。
標高は低いが、東側は荒川の河川敷が広がるので、天気に恵まれれば、好展望が得られる。
岩場の基部にあたる山腹を踏みならすと、ポンポンと音がすることから、この名がある。
ポンポン山については、『新編武蔵風土記稿』横見郡田甲村の条に「玉鉾山」として、次のような詳しい解説がある。
「社(注:高負比古根神社)の後背は高さ十一間ばかりなる巌石の丘にて、その内社によりたるあたりを踏み鳴せば鼓のごとく響きあるところあり。そこを玉鉾石と称す。また通じて玉鉾山とも号せり」と詳しい。
これによれば、ポンポンと音がする山腹を「玉鉾石」といい、岩山全体を玉鉾山(ポンポン山)という。
「この響は地下に洞窟があるという説と、ローム層と砂岩の境界面で音波がはね返るので音がするという2説がある」(『角川日本地名大辞典11 埼玉県』(角川書店、1980年
)。
私が最初に訪れた1970年代当時は、たしかに踏むとポンポンという音が確認できた。
しかし、最近の山行記録を読んでいると、踏んでも音がしないという報告が圧倒的に多い。
ところで、ポンポン山(玉鉾山)には、次のような伝説が残されている。
「その昔、ある長者が財宝の隠し場所を捜していました。長者はある日、高負彦根神社(高負比古根神社)に詣で、『いちばんいい財宝の隠し場所を教えてください』とお伺いをたてました。すると神様のお告げがあり、『この岩山に埋めろ。私が守ってやろう』というものでした。そこで長者は大変安心して、財宝をこの山に埋めたそうです。
それからしばらくして、長者の隠した財宝を盗もうと盗人が山に入り込みました。すると突然、山がポンポンと山鳴りを起こしたので、盗人は恐れおののき、震えながら山をおりました。それ以降だれも、財宝を盗み出しに行くものはいなかったということです。あまりにも古い話なので、その後の財宝の行方は、近在の人たちの間でも知る者はいなくなったということです。こうした話の名残として、岩山はポンポン山と呼ばれており、山には神霊がいるといわれています」(吉見町役場ホームページより)
ま
まくいわ 幕岩(小川町)
比企郡小川町下里(割谷地区)
第4回「仙元丘陵」
2万5千分の1地形図「武蔵小川」
2つの仙元山(青山の仙元山、下里の仙元山)にはさまれた仙元丘陵が槻川に沿ってL字型に曲がるちょうどその地点の山麓にあたる下里1区割谷(わりや)集落奥の千木(千騎)沢沿いの岩場「大日山」の向かいに、幕を張ったように横幅の広い岩場がある(高さ数十㍍、幅数十㍍)。
これが「幕岩」である。
幕岩には大蛇が棲んでいるとの伝説があり、大蛇が岩の上で昼寝をしているのを見た人もいたという。
まつごうとうげ 松郷峠(小川町・ときがわ町)
比企郡小川町上古寺・比企郡ときがわ町雲河原
第9回「慈光寺と都幾山・金嶽・士峰山」
2万5千分の1地形図「安戸」
右に小川町上古寺の鎮守・氷川神社の森をみて、車の通りが激しい県道西平小川線を登っていくと、右手に光兆産業(株)古寺砕石工場の広大な採石場が広がってくる。
荒涼とした光景で、目を覆いたくなるが、車道が砕石工場寄りに大きくカーブする個所で、かつての旧道が近道として辛うじて残っている。
旧道を歩き、再び車道に飛び出す少し手前の林のなかに芭蕉句碑が寂しく建つ。
内田康男氏によると、この芭蕉句碑は幕末の弘化3年(1846)に上古寺の三氏が建てたものであるという。
句碑の表には「蝶の飛ぶばかり野中の日かげかな」と刻まれている。
興味深いのは、句の下に「右山王天寺左八王寺大山道」とあることだ。
町田尚夫氏は「山王」をときがわ町西平の萩日吉神社、「天寺」を子ノ権現、「八王寺」を竹寺、「大山」を神奈川県伊勢原市の大山阿夫利神社であろうと推測している(町田尚夫『奥武蔵を楽しむ』(奥武蔵研究会、2004年)。
そこから、この句碑が寺社への道しるべを兼ねていたことが分かる。
松郷峠は、かつて各神社仏閣への交通の要衝として栄えた場所であったのであろう。
道しるべの文字は思い切って太い字、対照的に句は上部にさりげなく彫られており、見事なコントラストを見せている。
句の選定も、かつてのこの地にふさわしい。
『芭蕉の句を歩く』(さきたま出版会、1983年)の著者・小林甲子男氏も、「この碑は埼玉でも名碑の中に入るであろう」と賞賛されている。
しかし、新道ができ、車の通行量が増えたうえ、巨大な砕石工場の広がる荒涼たる光景に、往時の松郷峠の面影は全くない。
ちなみに、松郷峠は、芭蕉句碑から再度車道に出て、少し登った小川町とときがわ町との境である。
まつのきとうげ 松の木峠(ときがわ町)
比企郡ときがわ町大野
初出
2万5千分の1地形図「安戸」
ときがわ町が整備した「ときがわトレッキングコース」の一地点。
ときがわトレッキングコースは、ときがわ町西平の慈光寺入口バス停から始まり、慈光寺・霊山院・七重峠休憩所・森の広場をへて、急な木階段を登り切ると、「松の木峠」である。
堂平山南東山腹上の標高約800㍍圏。
峠名は地元(大野)呼称ではなく、トレッキングコース設置にともない、町が新たに命名したもの。
み
みかさやま 三笠山(小川町)
比企郡小川町青山
第6回「雷電山・御岳山・大峰とその周辺」
2万5千分の1地形図「武蔵小川」
小川町大字青山の八高線西側丘陵である「福寿山」(ふくじゅさん)の一峰。
福寿山のなかでは、主峰・御岳山(297㍍独標)に次ぐ、289㍍独標(ゴルフ場造成前の2万5千分の1地形図「武蔵小川」で「大峰山」と表記)。
三笠山の北には「八海山」があり、八海山には「八海山様」の石像、三笠山には「三笠山様」の石像が祀られていた(現在は、ゴルフ場造成にともない、いずれも御岳山山頂に遷座)。
青山上→八海山→三笠山→御岳山が「参道」となっていて、御嶽講の人々は八海山様・三笠山様に拝礼したあと、御嶽山座生大権現の石像にお参りをした。
三笠山の南に広がる小平地が「富士見平」であり、八海山・三笠山・富士見平一帯は秣場だった面影を残す小灌木と草地が混じる展望の良い明るい山だった。
富士見平の南が旧玉川村(現・ときがわ町)日影分の「大峰」(現在の2万5千分の1地形図「武蔵小川」で「大峰山」と表記されている293㍍独標)を含む日影側の丘陵)である。
残念ながら、1989年に始まる大成建設の「(仮称)武蔵台カントリークラブ」(現・アドニス小川カントリー倶楽部」)造成により、福寿山は御岳山以外すべて消失。
三笠山も、八海山・富士見平とともに姿を消した。
みすずやま 皇鈴山(皆野町・東秩父村)
秩父郡皆野町三沢・秩父郡東秩父村坂本
第11回「二本木峠・皇鈴山・登谷山」
2万5千分の1地形図「安戸」
二本木峠から登谷山にいたる尾根上の679㍍独標。
広い山頂は、外秩父主稜中最も展望が楽しめる場所である。
県道からの車が満載の駐車場は目障りだが、山頂には東屋やベンチもある、
さらに展望が良いのが、山頂東側の「展望台」である。
端には手すりが設けられ、手すりにつかまりながら、何も遮るもののない大展望を満喫できる。
展望台の下にはベンチが一つあり、一見、山頂から下に転げ落ちそうな感もあるが、こちらも展望台以上の臨場感のある眺望を楽しめる。
このベンチを「天空のベンチ」と呼んでいる。
さて皇鈴山の山名について、古い地誌にも記載が全くないし、どのような由来で、この大仰な名がつけられたのか疑問をもっていた。
それが氷解したのが、関口洋介氏の奥武蔵研究会会報『奥武蔵』第350号(2006年7月)の次の一文に接したときである。
「皇鈴山は、昭和11年、当時の三沢村の福田唯一村長がこの峰を初めて『皇鈴山』と命名し、山頂に皇鈴神社を祀ったと言われる」
念のために『三澤村誌』(三澤村誌刊行委員会、1977年)を古書店から取り寄せ確認したところ、次の一文があった。
「皇鈴山は昭和11年。時の村長福田唯一氏の発議により三沢公園として誕生し、皇鈴神社を祭り、春秋の二季に日を定めて全村民相寄り一日の融和を楽しんだという」
村誌の一文では、皇鈴山の名を福田村長が命名したとは明言していないが、山頂に三沢公園を設置するにあたり、村の象徴として山名を同時に命名したと考えて無理はないだろう。
皇国思想が反映されたような皇鈴山という山名も、昭和11年(1936年)という太平洋戦争に向かう時代の雰囲気を感じさせる。
ところで、戦後の昭和25年(1950年)、皇鈴山頂に皆野町(旧三沢村)出身の夭逝の俳人・持田紫水(もちだしすい)(1917~1943)の句碑が建立された。
紫水はようやく新進の俳人として頭角を現した矢先の昭和15年(1940年)、23歳で応集を受け、南方に派遣された。
応集中の昭和17年(1942年)、5つの句により馬酔木賞を受賞したが、昭和18年(1943年)戦地で胃腸カタルにかかり、故郷の三沢村に戻り療養していた。
だが同年11月8日、26歳の若さで他界した。
皇鈴山山頂に建立された紫水の句碑には、表に「いっしんに鷹みてありぬ萱は穂に 紫水」と彼の句が刻まれた。
碑の裏には、彼の師であった金子伊昔紅による次のような紫水の略歴が刻まれている。
「持田紫水は大正6年1月29日三沢村に生まれ、俳句を好み、伊昔紅、かけいに学び水原秋桜子先生の馬酔木に寄稿して馬酔木賞を受く、昭和18年11月8日病没す」
毎年5月5日が山開きであり、当日は皆野町主催の行事が盛大に行われている。
みつごいわ 三つ児岩(小川町)
比企郡小川町高見
第14回「四ツ山(四津山)・物見山・堂ノ入山・たかんど」
2万5千分の1地形図「三ヶ尻」
高見地区・四ツ山(四津山)の二の沢にあるという三つに割れた大岩。
この岩については、いろいろな伝説があるが、そのうちの2つは以下のとおりである。
「3歳になる神様(大男)が、どこからか頭の上に岩を乗せてきて、四津山で一休みした時、その岩を放り投げたのが、この三つ児岩という。今でも岩に頭と手のついた跡(後刻か)がある。大岩が3つに割れたという。一休みした時、足をついたのが、足っこ沼(一の字沼)と牟礼の足っこ沼といわれ、両方足の形をしている。この三つ児岩のところに小さなお宮があり(今は確認できない)、正月飾りを持って行ったという」
「昭和55年作成の『八和田地区郷土かるた』によると、「奇石で残る三つ児岩」の説明に高見地区四津山の二の沢にある巨大な岩を三つ児岩という。伝説によれば、戦国時代、四津山城の築城祝いに、石井九郎左衛門の家来の中から、七・五・三の兄弟が選ばれて、舞を奉納中、突風が起こって春雷となり、山を下りることができなくなった。年下の七歳、五歳の子供は、家来たちに助けられたが、三歳の子供は風に飛ばされて岩まで吹き飛ばされてしまった。それ以来、大正の末期までの約300年の間、三歳の子供は山に登らせない風習が残っていた」とある」(いずれも、内田康男「小川町の山々・巨岩・名石ーその歴史と伝説ー」リリック学院 懐かしき小川町 03ー⑤、2022年2月19日作成より引用)
みどうやま 御堂山(嵐山町)
比企郡嵐山町太郎丸
第13回「大立山・二ノ宮山・高根山」
2万5千分の1地形図「武蔵小川」
太郎丸の入口にある80㍍前後の小山。
しかし、そんな小山ながら興味深い伝説や信仰を秘めている。
登り口には馬頭観音があり、石段を登った中腹には堂宇がひっそりとたたずむ。
かつて、この堂宇内に金箔の聖観音像が納められ、近在の信仰が厚かった。
しかし、1960年代末に、何者かに盗まれてしまった。
堂宇の左手から登りつめた山頂は小平地で、金比羅神社、秋葉神社、愛宕神社の三つの小祠が鎮座。
聖観音が健在だった頃には、金比羅神社を合わせて1月10日に祭礼を行っていた。
また、8月12日には村中の人々が聖観音の前に集まり、酒を酌み交わしたという。
しかし、聖観音が盗まれてしまってからは祭礼も簡素化され、1月3日に淡州神社の新年祭の時、ついでにしめ縄を張り、幣束をあげる程度。
山頂を公園化するという話もいつしか立ち消えになってしまった。
御堂山にまつわる巨人伝説を、ひとつを紹介しておこう(韮塚一三郎編著『埼玉県伝説集成 上・自然編』(北辰図書出版、1973年)。
「嵐山町広野に大田坊(ダイダンボウ)というところがある。伝えるところによると、昔ダイダン坊という大男が土をたくさん入れた籠を背負ってここを通った。そのときの足跡の一つが広野のダイダン坊堰付近に残り、もう一つの足跡は滑川町羽尾付近にある。また、籠のメド(すき間)から土がこぼれ、太郎丸の御堂山になった。メド山が、いつの間にか御堂山になったのである」
む
むじないわ ムジナ岩(東秩父村)
秩父郡東秩父村奥沢
第2回「官ノ倉西尾根とその周辺」
2万5千分の1地形図「安戸」
細窪山東側鞍部より奥沢に少しくだった山林中にある。
大きな穴が空いていて、そこにムジナが棲んでいたので、戦前子どもたちは、煙でいぶしてムジナを捕えようとしたことあったという。
め
めがいわ 女鹿岩(ときがわ町)
比企郡ときがわ町西平
第6回「雷電山・御岳山・大峰とその周辺」
2万5千分の1地形図「武蔵小川」「安戸」
雷電山から南に下がる尾根が女鹿岩の集落にぶつかる付近にある大岩。
天王山(堂山)から縦走する場合は、途中で女鹿岩にくだるのではなく、雷電山まで登り、雲河原からの林道をくだる方が分かりやすい。
林道から少し入ったところにある墓地からくだったところが女鹿岩の岩上である。
高さ10㍍ほどの大岩が2つに割れた状態にあり、割れ目にはチョックストーンがはさまっている。
雷電山の女鹿岩は、都幾川をはさんで向かい合う奥武蔵の「弓立山」(ゆみたてやま)北側の背筋コース上にある男鹿岩(おがいわ)と対の関係にあり、次のような大蛇伝説が有名である。
「昔女鹿岩には雌の大蛇が棲み、弓立山の男鹿岩に棲む雄の大蛇と毎年1回、7月7日の夕方になると、都幾川のほとりで逢瀬を楽しんでいた。
しかし、ある夏激しい日照りが続き、雌の大蛇が姿を消してしまった。
これを悲しんだ雄の大蛇は涙を流し、雌の後を追って行って姿を消してしまったという。
も
ものみやま 物見山(東秩父村)
秩父郡東秩父村御堂・安戸
第7回「笠山前衛の山々」
2万5千分の1地形図「安戸」
東秩父村御堂の萩ノ平では、リュウゴッパナ(493.8㍍3等三角点:点名「竜ヶ鼻」)西の「ツルキリ」(ツルキリ山」から尾根を北に進んだ460㍍圏ピークを「物見山」と呼んでいる。
今は展望なしの山だが、かつては四方を望見できたという。
ものみやま 物見山(東秩父村)
秩父郡東秩父村安戸
第7回「笠山前衛の山々」
2万5千分の1地形図「安戸」
東秩父村安戸の寺岡や帯沢などの集落の人々は、ツルキリから北に延びる稜線上の411㍍独標から東に派生する支稜上の300㍍圏ピーク(送電線鉄塔がたっている)を物見山と呼んでいる。
前項の萩の平の物見山と同様、松山城の支城にあたる腰越城の物見櫓が比企郡、いずれの山頂にも築かれていたのかも知れない。
そういえば、この付近には笠山郡界尾根上の「タカハタ」(高旗山・高畑山:山頂に旗を掲げて腰越城に合図をしたという)など、城跡と関連した地名が残されている。
ものみやま 物見山(東秩父村・寄居町)
秩父郡東秩父村大内沢・大里郡寄居町西ノ入
第2回「官ノ倉西尾根とその周辺」
2万5千分の1地形図「寄居」
金山・君八山を過ぎると、官ノ倉西尾根は右に乳首状の特異な浅間山」(仙元山)をピークを眺めながら、送電線の下を歩くようになる。
いくつかのピークがあるが、「東京電力西上武幹線181号鉄塔」のあるピーク。
名称は、比企・秩父・大里地方に多い「物見山」と同じ。北条氏の主要城の物見の砦ないし櫓があったと(大内沢の物見山の場合、距離的に近い鉢形城の物見砦)と想像される。
官ノ倉西尾根は、物見山の次のピークで方向を45度右に変え、286.6㍍4等三角点峰(点名は「大内峠」)をへて、寄居町三品の高山(石尊山)にいたる。
ものみやま 物見山(比企郡ときがわ町・比企郡小川町)
比企郡ときがわ町五明・比企郡小川町下里
第4回「仙元丘陵」
2万5千分の1地形図「武蔵小川」
仙元丘陵のほぼ中央にある286㍍独標。
2万5千分の1地形図「武蔵小川」でも「物見山」と表記しているのにすぐ分かるだろう。
顕著なピークではなく、単なる尾根上の小平地という印象で、「物見山」と書かれた山名表示板がなければ、気づかず通りすぎてしまう。
そんな平凡な山容の物見山だが、西側の青山城(割谷城)と東側の小倉城との中間地点にあり、戦術上重要な役割を果たしていた。
さらに、槻川に落ち込む断崖という自然の要塞をもつ北側、急な尾根が落ち込む東側・南側にくらべ、緩やかな尾根が続く南西側は、小倉城の防御上の最大の弱点であった。
そのために、西側から尾根を伝って押し寄せる敵兵の到来を、小倉城に伝えるための最前線こそ物見山であった。
あるいは、青山城(割谷城)からの知らせで、尾根を伝って敵兵が押し寄せることを小倉城より前に知り、敵兵の侵攻を一時阻止し、時間稼ぎを図るための防御線をなしていたかも知れない。
残念ながら山頂は樹林に覆われ、展望はない。
そんな平凡な山頂の物見山だが、古くは『武蔵通志』に「高さ九尺六十尺。玉川村五明の北にあり」と記されている。
それ以外にも、『武蔵國郡村誌』比企郡五明村の条では、「物見山 高さ九十六丈。周囲不詳。村の北方にあり、嶺上より二分し、北は下里村東西南は本村(=五明村)に属す。山脈雷電山に連る樹木鬱葱。字赤坂より上る九町四十八間三尺」と、かなり詳しい。
『郡村誌』比企郡田黒村の条にも「物見山」の名が見られ、次のように説明されている。
「高さ及周囲不詳。村の西北にあり、嶺上よ三分し、東南本村に属し、西は五明村、北は下里村に属す。村の中央より上る十三町。芝のみ生す」とある。
ここでいう「物見山」が、果たして2万5千分の1地形図「武蔵小川」の286㍍独標、すなわち物見山を指すのかについては、町田尚夫氏の指摘するように疑問がある(町田尚夫『奥武蔵をたのしむ』さきたま出版会、2004年)。
何より、物見山は小川町下里とときがわ町五明(ごみょう)の境にある山であり、ときがわ町田黒とは接していない。
町田氏はそれを根拠に、『郡村誌』田黒村の「物見山」は、右隣にある「仙元山」を指すのではないかと考察されているが、私もそれに同意したい。
なぜ田黒に属さない「物見山」の名が田黒村の条に記載されることになったのか、その経緯については、不明である。
ちなみに、物見山の山名は旧玉川村(現ときがわ町)五明側の呼称であり、小川町側の下里では無名峰である。
ものみやま 物見山(比企郡嵐山町・比企郡小川町)
比企郡嵐山町遠山・比企郡小川町下里
第5回「遠ノ平山とその周辺」
2万5千分の1地形図「武蔵小川」
武蔵嵐山公園のある大平山から北上する尾根が途中で急激に方向を南西に変え、嵐山町と小川町との境界尾根となり、観音山(下里観音山)から愛宕山の尾根の南に並走。
寺山を最後に槻川に落ち込む。
この境界尾根上で最も目立つピークが214㍍独標である。
このピークを、南側の嵐山町遠山では「物見山」と呼んでいる。
『武蔵通志』に「物見山 高さ五百尺。菅谷村遠山の北にあり。西は寺山及下里観音山、愛宕山に連なる」と記されている山は、下里・遠山の境界尾根上の214㍍独標、すなわち「物見山」であろう。
「寺山」の項でも引用した「菅谷村の沿革」でも、遠山村の地形に触れ、「北に物見山を背負い、この山脈があたかも屏風のように連り左右に開いて東は大平山、西は寺山で止まっている」と記している。
この描写だけからも、遠山の北に屏風のように連なり、東の大平山、西の寺山に挟まれた物見山の位置が、214㍍独標であることには疑う余地はない。
山名由来は、比企に多数ある同名の山と同様、山頂に物見櫓ないし物見砦があったことによる。
小倉城が至近距離である頃から、下里の物見山(214㍍独標)は、仙元丘陵の「物見山」と同じく、南西側の尾根からの攻撃に一縷の不安のある小倉城の西側至近距離の物見櫓として、敵の西からの来襲を告げる役割を果たしていたと思われる。
ところで、昭文社「山と高原地図23 奥武蔵・秩父」では、長年、物見山(214㍍独標)のことを「寒沢山」と呼称していた、
大石真人氏は「奥武蔵辞典-山名編ー」(『マウンテン・ガイドブック・シリーズ8 奥武蔵』朋文堂、1960年版所収)において、「かんざわやま 220㍍ 武蔵嵐山の西、遠山部落の脊稜をなす山容のゆたかな山である」としているが、ここで「寒沢山」とされているのは、明らかに「物見山」である。
寒沢山は、物見山(214㍍独標)西の尾根上の四辻(そのまま西に寺山に行く道、北西に観音山~愛宕山の尾根に行く道、西に220㍍圏ピークに行く道の3つの道と、物見山に戻る道の4つの道が交差する四辻)から西に進んだ下里寒沢集落の奥にある220㍍圏ピークである。
残念ながら、大石氏の誤りを昭文社山と高原地図23『奥武蔵・秩父』で踏襲。
214㍍独標に寒沢山と表記し続けたため、現在でも物見山山頂に「寒沢山」と記された私設の山名表示板があるなど、混乱を招いてきた。
現在では、昭文社山と高原地図23『奥武蔵・秩父』(2025年版)で、寒沢山の表記が正しい位置に表記されているので、是非、214㍍独標に物見山の名を表記して欲しいものである。
ものみやま 物見山(小川町・寄居町)
比企郡小川町木呂子・大里郡寄居町三ヶ山
第3回「金勝山とその周辺」
2万5千分の1地形図「寄居」
寄居町三ヶ山との境である小川町大字木呂子字群窪にある197㍍独標。
かつて鷲丸山のあった「ホンダ埼玉製作所 完成車工場」の西側。
山の北側は土砂砕石場跡、東側はホンダ寄居工場の駐車場、西側は埼玉県廃棄物最終処分場を含む「彩の国資源循環工場」など開発が進み、そのなかで孤軍奮闘のかたちで山を死守している物見山も、北山稜が土砂採掘により一部削られている。
それでも北側の展望に恵まれ、寄居町の市街が一望できる。
木呂子の物見山は、その名称から単なる鉢形城の物見櫓跡かと思っていたが、山頂には祠の基石らしきものが転がっており、堀切と小平地の城郭の遺跡が残っていることなど、物見櫓より規模の大きい「砦」ないし「城」の可能性もある(藤本一美『比企(外秩父)の山々』(私家本、2018年)。
実際、中田正光氏は、『埼玉の古城址』(有峰書店新社、1983年)において、小川町木呂子の物見山について、吉野城とし、「伝えの城であろう」としている。
しかし、「吉野城」(吉野砦)」の所在地と比定される場所については3説あり、いずれも小川町大字木呂子の字群窪(物見山)のほかに、八高線北の字万所、八高線南の字下万所の説もある。
私は1986年、勝呂の宮沢貞夫さんに「下万所」(しもまんどころ)の吉野砦跡と呼ばれる場所にご案内いただいた。
現地は八高線脇の高台にあり、振り返ると小川町方面が一望される。
したがって、かつての鉢形城の見張りの砦が築かれていた「ことが想像される。
宮沢氏によると、何か異変があったときは、ここから1キロほど北に進んだ寄居町境の物見山(本稿の197㍍独標:眼下に鉢形城が望まれる)まで伝令が走り、烽火を上げて鉢形城に連絡したのではないかという。
宮沢氏に前記の中田氏の説(吉野砦跡=物見山)を説明したところ、それは間違いで、物見山と吉野砦は別物であると語っておられたのが記憶に残っている。
ともあれ、吉野砦(吉野城)の所在地に関する3説は、いずれも決定打を欠くのが現状のようだ。
なお、吉野砦(吉野城)の城主については、松山城主・上田能登守朝直(暗礫斎)の家臣・木呂子丹波守と伝えられるが、真偽のほどは定かではない。
ものみやま 物見山(寄居町)
大里郡寄居町牟礼
第14回「四ツ山(四津山)・物見山・堂ノ入山・たかんど」
2万5千分の1地形図「三ヶ尻」
小川町高見の四ツ山(四津山)(高見城址)から北西に延びる尾根の最後を飾る山。
かつて物見山山頂には190.1㍍3等三角点が埋設されていたが、(株)NXワンビシアーカイブス関東第3センターの建設にともない、山の北半分と山頂が削り取られた。
現在、山頂がない状態ながら南半分は残されている。
四ツ山からの縦走路は、現在、物見山南山腹を通る踏跡に付け替えられており、牟礼の集落にくだることができる。
造成により、山頂の三角点は四ツ山へ尾根から北東に派生する支尾根上に移設され、標高は168.6㍍に変わった(点名「牟礼」はそのまま)。
移設された3等三角点のある地点に「愛宕山」なる私設の山名表示板があるが、地元名称かどうか確認できていない。
物見山山頂に祀られていた小祠は、山麓の熊野神社に遷座されたという。
「物見山」の名称は、鉢形城の物見櫓が山頂にあったことによる。
ものみやま 物見山(東松山市・鳩山町)
東松山市岩殿・比企郡鳩山町石坂
初出
2万5千分の1地形図「武蔵小川」
東松山市岩殿と比企郡鳩山町石坂との境界にある134.9㍍2等三角点峰(点名「石坂」)。
山頂には展望台が建てられ、360度の眺望が楽しめる。
また、ツツジの名所でもある。
県道343号岩殿岩井線をはさみ、北側には板東三十三観音霊場第十番札所「巖殿山正法寺」(いわどのさんしょうぼうじ)がある(東松山市岩殿)。
正法寺は「岩殿観音」の俗称で親しまれているが、物見山・岩殿観音のある丘陵一帯を「岩殿山」という。
岩殿山は、「かつて四十八峰九十九谷といわれたほど起伏に富み、関東平野が一望できる景勝地として県名勝地物見山観音の勝として指定されている」(『角川日本地名大辞典11 埼玉県』角川書店、1980年)。
物見山には、坂上田村麻呂の東征にまつわる伝説が残されている。それによれば、「(坂上田村麻呂は東征のとき、)この山に登り、四囲を眺めたとことによる山名といわれています。また、このとき北方の雪解沢に潜む悪竜を退治したともいわれています」(東松山市ホームページより)。
東松山市ホームページによると、「(物見山)山頂に立てば、遠くは箱根、足利、大山、富士山、秩父、信越、上野、下野、常陸の諸山から東京湾まで望むことができるといわれています」という。
や
やまとみず 日本水(寄居町)
大里郡寄居町風布
第12回「釜伏峠・葉原峠・大平山・金ヶ嶽・金尾山」
2万5千分の1地形図「寄居」
釜伏峠の釜山神社から奥宮のある釜伏山(男釜)に登り、そこから岩尾根をくだった鞍部より左に断崖をへずるようにして進んだところにある。
古い地誌にも複数登場する昔からの名水である。
『武蔵国郡村誌」秩父郡風布村の条でも、「峯(引用者注:男釜)より北方一町を下り、岩の間より清水湧出し旱魃淫雨の候といえども、かつて増減せざるをもって、土人これを一盃水と呼ふ』と記述している。
『武蔵通志』でも、「(釜伏嶺の)頂上に釜山神社あり。日本武尊を祭る。その北に下る一町ばかりに一盃水あり。岩隙より湧出し」とある。
これらの記述から想像されるように、日本水はかつて「一盃水」(一杯水)と呼ばれていたことが分かるうえ、大岸壁の間から湧き出る様子が手にとるように分かる。
実際に「日本水」は、百畳敷岩と呼ばれる30㍍もの高さの岸壁の下部の岩の割れ目から水がこんこんと湧き出ている。
日本水は涸れなかったため、旱魃路の雨乞い行事の「もらい水」になったという。
つまり、「一般には、この水を汲み、若者たちがリレー式に村まで運び、畑にまいて降雨を祈った。そこで水をもらいに来るのは遠方の村々で、地元の村では、わざと遠方の城峰山方面等にもらいに行ったという」(飯野頼治『山村と峠道-山ぐに・秩父を巡る』(エンタプライズ、1990年)
飯野氏は続けて、次のように書いている。
「この日本水は、日本武尊が岸壁に剣を刺して、戦勝を祈願したところたちまち湧出し、あまりの冷たさから一杯しか飲めなかったところから『一杯水』とも言われている。また、不老長寿や子授けなどの願いごとにご利益のある霊水としても、古くから近在には知られていた。環境庁が選定した名水百選にも風布川源流『日本水』として選ばれた(飯野頼治、前掲書)。
このように昔から霊水として有名で、名水として有名な日本水だが、現在では、百畳敷岩が崩落する危険があるため、立ち入り禁止となっている。
やまのかみごえ 山ノ神越え(小川町・東秩父村)
比企郡小川町飯田・秩父郡東秩父村安戸
第1回「官ノ倉山とその周辺」
2万5千分の1地形図「安戸」
官ノ倉山西峰(石尊山)西肩から城山(腰越城址)へ続く尾根上にある峠。
東秩父村安戸から小川町飯田の飯田ダム奥に越える峠。
昭文社山と高原地図23『奥武蔵・秩父』にも「山ノ神越」と表記されている。
ただし、地元・飯田では単に「山ノ神」と言っている人の方が多い。
山ノ神越えには、安政6年(1859)5月に比企郡飯田村で建てた山ノ神の小祠が祀られている。
ここも、かつて安戸から笠原や飯田、腰越への「花嫁の越えた峠」であった。
現在でも、毎年1月17日に山ノ神を信仰している飯田の人たちが登拝している。
石尊山西肩から城山(腰越城址)への尾根には、このように東秩父村安戸から小川町へ越える峠が、山ノ神越え(山ノ神)以外にも、「小瀬田越え」「桜山」などいくつも存在する。
小川町笠原から東秩父村安戸に出るためには、急峻な官ノ倉山を越えるよりも、いったん飯田や腰越に回り、山ノ神越え、小瀬田越え、桜山などの峠を越えた方がずっと楽だったという。
なお、山ノ神越え(山ノ神)は、小川町・東秩父村の町村界尾根上にあるため、東秩父カントリークラブの造成を免れ、現存している。
しかし、山ノ神越え(山ノ神)の先で尾根は町村界を外れ、腰越城址北の249.3㍍三角点峰まで完全に東秩父村に入ってしまうので、この間の小瀬田越え、桜山は東秩父カントリークラブ造成にともない消失してしまった。
山ノ神越えの安戸側登路も、東秩父カントリークラブの造成により消滅した。
今は、飯田側からの道が残るのみである。
よ
よつやま 四ツ山(四津山)(小川町)
比企郡小川町高見
第14回「四ツ山(四津山)・物見山・堂ノ入山・たかんど」
2万5千分の1地形図「三ヶ尻」
小川町の北部。寄居町との境界に近い大字高見に位置する四ツ山(四津山)。
『新編武蔵風土記稿』比企郡高見村の条は、「増田重富蹟」に続き、その場所について以下のように記している。
「坤(ひつじさる)の方にあり、そこを四ツ山と呼ぶ」
『武蔵郡村誌』比企郡高見村の条は、「四ツ山 高さ三十六丈。周囲不詳。村の西方にあり、山脈西方今市に村に連なる。樹木鬱蒼。字深田谷より上る五町十五間」と記す。
『武蔵通志』も『郡村誌』の記事を一部踏襲。
「四(ヨツ)山 高さ三百六十尺。男衾村今市の南にして、比企郡八和田村高見に属す。四峯並立するをもって四山の称あり。高見字深田谷より上る五町余。頂に愛宕社あり。北は荒川を望み、景勝の地なり」と記す。
明治19年(1886)の「高見村地誌」はさらに詳しい。
「山嶽 四ツ山。所在 本村(注:高見村)西南字四ツ山。形状 その様、山を四個並立したりごとくなるをもって四ツ山の称を付せりという。村中の一大高山にして、山派左右に分かれて、南麓は全郡高谷村に境し、西は男衾郡今市村境なり、平地中より突立し、岩石峩々とし、高谷村の旗峠と相対す。高さ 三十六丈。周囲 十七町五十五間。登路 一条あり、本山の東北字深田谷より登る。屈曲険岨なり。その程は五町十五間松樹多し。景到 頂上は一平坦をなし、愛宕社祠あり。山中ツツジ多く、花時の風景最も愛すべし。四方の眺望実に眼を驚かせり。北方流水は荒川にして、布白を延かごとく地方眺望一等地と称せり。雑項 頂上愛宕社は毎年3月24日をもって祭る。地方人民群参す。当山昔時城跡なり。城主増田四郎重富という人住みせしと言い伝う。豊臣秀吉関東征伐の際に廃城の由を里伝す。その証誌なし」(小川町教育委員会所蔵八和田村行政文書336)
これらの地誌が述べるように、関越自動車道と市野川にはさまれた寄居町今市付近から遠望すると、台地状の山の上に四つの小さな突起が確認できる。
まさに「四峯並立」「四個並立」する山容である。
ここから「四ツ山」の名が生まれたということがよく分かる。
現在では「四津山」の表記が一般的だが、もともとは「四ツ山」と表記されていた。
四ツ山(四津山)の山頂には、大字高見の鎮守・四津山神社が祭られている。
『通志』や「高見村地誌」に記述されているとおり、もともと四ツ山山頂に祀られていたのは「愛宕神社」(愛宕社)であった。
愛宕神社は、もとは麓の明王寺の境内鎮守で、氏神として寺に祀られていた。
その後、現在の鎮座地である四ツ山山頂に遷座された。
当時の神社は、寺が奥ノ院として京都から遷座した愛宕様の本体を祀っていた。
それが現在四津山神社の社殿内に安置されている勝軍地蔵である。
勝軍地蔵は、高さ30センチほどの白馬に乗った見事なものである。
その後、明治40年(1907)の政府による神社統合により、村内の11社を四ツ山の愛宕神社に合祀。高見村の村社(鎮守)とした。
このとき、神社名を愛宕神社から、地名(四ツ山)にもとづき「四津山神社」に改称した。
本来は神社名が「四津山神社」で、神社のある山名は「四ツ山」であるが、「四津山」の表記が神社名、山名として定着した感がある。
しかし、本ブログでは、もともとの山名表記である四ツ山を尊重。「四ツ山」(四津山)と併記することにしたい。
四津山神社参道入口の石鳥居を抜けると、山頂までは162段の石段となる。
石段は下と上に分かれ、下の47段は比較的緩やかだが、上の115段はかなり急な石段である。
参道入口から約20分。
急な石段を登り切ると、芝生の山頂に比較的新しい四津山神社の社殿が鎮座する山頂一角につく。
現在の社殿は、1997年11月に建立された新社殿である。
山頂からは北側の展望が開け、眼下には荒川の向こうの深谷・熊谷の市街。さらに冬なら雪をまとった榛名、赤城、谷川、日光白根など北関東の山々が一望でき、時間を忘れるくらいである。
「高見村地誌」のいう「地方眺望一等地」の名がふさわしい山頂からの好展望である。
ところで、四津山には中世の山城・高見城が築かれていた。
『新編武蔵風土記稿』比企郡高見村の条は、「増田重富居蹟 坤(ひつじさる)の方にあり、其所を四ツ山と呼ぶ。ここは増田四郎重富といいし人の居蹟といい伝うるのみ。その事蹟詳ならず。されど男衾郡野原村文珠寺に重富の塚あり」と記す。
『武蔵国郡村誌』比企郡高見村も、ほぼ同じ内容で、「増田四郎重富居蹟 方十五間ばかり。村(高見村)の西方四ツ山の嶺上にあり、四囲土手の遺形猶存す。古昔増田四郎重富といいし人の居蹟と云い伝うるのみ。其の事蹟詳ならず。されど男衾郡野原文珠寺に重富の塚あり」と記している。
増田四郎重富といえば、熊谷市(旧大里郡江南町)野原の文珠寺を再建した人物であり、彼の塚が文珠寺にあるというのも頷ける。
『郡村誌』には、増田四郎重富は「長享元年(1487)二月三日卒せしといえり」とある。
中田正光氏は、築城者については明確には分からないとしつつも、高見城の位置づけとして、鉢形城と松山城の中間地点にあり、杉山城などとともに、当時の街道を押さていたとしている(中田正光『埼玉の古城址』有峰書店新社、1983年)。
遺構図と2万5千分の1地形図「三ヶ尻」を照合すると、現在の四津山神社付近が高見城の本郭、神社参道が大手口に当たっている。
広い山頂の神社北北西に堀切をはさんで二の郭。
さらに山頂一帯では一番標高の高い(200㍍圏)地点に三の郭が尾根に沿ってつくられ、三の郭北端の堀切は高さが5メートルを超えている。
最北端の堀切を抜けると、尾根は急なくだりとなり、小川町・寄居町の境界鞍部に落ち込む。
内田康男氏は「増田家文書」を解読し、文明10年(1478)、古河公方足利氏家臣の増田四郎重富は、深谷市上増田からこの地に移り、高見城を築いたとしている(小川町遺跡調査会『四津山』1997年)。
その2年前の文明8年(1476)、山内上杉氏家臣の長尾景春が鉢形城に立てこもって、主君に離反する事件(長尾景春の乱)が起きた。
これに対し、扇谷上杉氏は重臣の太田道灌を派遣し、文明12年(1480)、太田道灌の軍勢は一時、高見城に布陣したといわれる。
文明18年(1486)、扇谷上杉氏の当主・上杉定正が家臣の太田道灌を暗殺するという事件が起こった。
太田道灌の死後、太田氏は山内上杉氏に属するようになり、扇谷上杉氏は古河公方と結びつき、両上杉氏は激しく敵対するようになった。
古河公方方の扇谷上杉氏(上杉定正)は河越城に、そして山内上杉氏(上杉顕定)は鉢形城を拠点とし、各地で争いを起こした。
そして、長享2年(1488)11月3日から15日の間、両者が激突する高見原の合戦が行われた。
「増田家文書」によると、高見原合戦の時、高見城は古河公方方家臣(扇谷上杉側)の増田四郎重富が城主で、その翌年、高見城は山内上杉顕定に攻められ、落城。それとともに、増田四郎重富も自害したと伝えられている(『郡村誌』では、増田四郎重富の死亡年を長享元年(1486)としているが)(以上の記述は、小川町遺跡調査会『四津山』1997年にもとづく)。
ところで、小川町高見に鎮座する四津山神社の春祭りは、毎年4月24日に行われる(現在はそれに近い日曜。2004年は4月21日・日曜)。
この春祭りのことをお日待ちといい、神楽が奉納される。
四津山神社の氏子の区域は、大字高見1区と2区、大字能増の旧2区である。
祭りにあたっての役割は、総代(5名)・用(10名)が中心になり、祭事・神礼・神楽・炊事などを分担して行う。
祭りの前日は氏子の人たちが総出で、祭りの準備を行う。
神社の境内にたてる万灯の花づくりを集会所に集まって作る。
万灯に飾る花は、紅白の色紙でつくる。これは女の人たちの役割である。
男たちは、竹を鉈で小割りにして節を削り取り、花をつける枝に使うヒゴ作りを行う。
万灯には「風雨順時」「五穀豊穣」「交通安全」「○○氏子中」と四面に文字が書かれ、農耕を始めるにあたり豊作を祈願する意味が込められている。
さらに祭りに来る参詣者に振る舞われる紅白の三角餅を作る。
餅は、白二、紅二の四臼たく。
これらの作業は祭りの前日に行われる。
祭りの当日になると、朝早く、幟旗をたてたり、若い人たちは、神楽の道具の前日に作った万灯、飯台に入った三角餅などの重いものをもって急な石段や斜面を登り、山頂の神社まで運びあげる。
午前10時頃になると、神楽殿から神楽の笛や太鼓の音があたりの山々に響きわたる。大里郡花園町永田の金鑚神社永田組(現在は深谷市金鑚神社永田組:深谷市無形文化財)の人たちが奉納する神楽。
この神楽は、児玉郡神川町の金鑚神社の名前に由来し、児玉郡から大里郡にかけての県北部に伝承されてきた。
当日奉納される神楽は、神々を題材にした一座形式で、禊(みそぎ)、岩戸開き(いわとびらき」の演技が午前中に奉納され、午後からは氷の川(ひのかわ)、湯探(ゆさぐり)、そして最後に種蒔(たねまき)などの演目が行われる。
最後の神楽である「種蒔」の最後に、天狐、アシライ、豊受大神たちが参詣者に紅白の三角餅を神楽殿から蒔く。
この餅を食べると、一年間無病息災でいられるとされ、とても縁起の良い餅である。
このとき、境内に立てられた万灯の花も氏子たちをはじめ多くの参詣者が競って大事に持ち帰る(以上は、小川町遺跡会『四津山』1997年にもとづく)。
2024年4月21日(日)に行われた四津山神社祭典では、午前10時から神楽殿で、金鑚神楽永田組(深谷市無形文化財)による神楽が奉納。
午後2時からの祭典後には三角餅を蒔いて見物客に差し上げるほか、中学生以下の子どものために、クイズに答えると景品やジュース・焼きそばなどがもらえる催しを準備した。
ら
らいでんやま 雷電山(ときがわ町)
比企郡ときがわ町日影・雲河原
第6回「雷電山・御岳山・大峰とその周辺」
2万5千分の1地形図「武蔵小川」「安戸」
ときがわ町町日影(旧玉川村日影)とときがわ町雲河原(旧都幾川村雲河原)の境に位置する3等三角点峰(点名は「日影」)。
山名は、各地の雷電山・雷電神社と同様、雨乞いを祈願した雷神を祀ることを由来する。
一時期樹林の一部が伐採され、展望の良くなった時期もあったが、今は樹林に覆われた展望の得られない暗い雰囲気の山頂である。
山頂には、日影の信仰の厚い雷電様の木の祠が日影を向き、そして雲河原の信仰を集める金毘羅様の木の祠が、まるで競い合うかのように雲河原を向き、祀られている。
つまり、雷電山という山名は、日影の雷神様に由来するもので、日影側の呼称である。
雲河原では、雷電山の名称がメジャーになったが、今でも「金毘羅山」と呼ぶ人もいる。
なお、山頂には雷電様。金毘羅様の小社以外に、2つの石の祠が祀られている。
それでは、古い地誌を見てみよう。『新編武蔵風土記稿』比企郡日影村の条では、小字名として「雨乞尾根」の名が挙げられ、「雲瓦村の境にある山をいへり」と記されている。
『風土記稿』の比企郡雲瓦村の項に「雷電山 村の南の方、平村との境にあり」と書かれてが、これは日影との境にある雷電山を指しているとは思えない。
ときがわ町の瀬戸元下(せともとしも)には、山頂に瀬戸雷電神社を祀る雷電山があるが、こちらでもない。果たして、どこを指しているのだろうか。
次に『武蔵国郡村誌』はもっと具体的に雷電山・金毘羅山について記している。
『郡村誌』比企郡日影村の条では、「雷電山 五十七丈六尺。周囲本村限り、一里八町。村の西方にあり、嶺上より三分し西は雲河原村に属し、南は別所村に属し、北は上古寺村に属す。山脈上古寺村雲河原村に連る。樹木鬱蒼。村の東方字高谷より上る三十町。険岨」と詳しく記述されている。
『郡村誌』比企郡雲河原村の項を見ると、「金毘羅山 高さ及び周回不詳。村の東北にあり、嶺上より二分し、東北は日影村に属し、西南は本村に属す。村の東北字入口より上る三町。雑樹生す。大樹なし」と、金毘羅山が雷電山の雲河原側の呼称であったことを示している。
なお、『武蔵通志』も金毘羅山、雷電山を別々に記述し、前者は「平村雲河原の東北にあり」、後者は「高さ五百七十六尺。玉川村日影の西にあり」と、それぞれ短い説明にとどまっている。
ところで、1989年2月の玉川村(現ときがわ町)日影の小北(こぎた)集落での聞き取りで、雷電山における雨乞いの様子が分かってきたので、以下記すことにしたい。
小北の古老によると、昔、雷電山に雲がかかったときには、必ず雨が降ると、父親が口癖のように言っていたという。
実際に、田植え時前に雷電山に雲がかかると、大抵雨が降ったという。
小北の別の古老によると、村社である日影神社に奉納されている太鼓を叩きながら、雷電山に登拝し、日影神社の神官が山頂の雷電神社に祝詞をあげたという。
また、榛名山に水をもらいにいき、もらってきた水を日影神社にあげたあと、太鼓を叩きながら、雀川の三つの堰(上流から大堰・中堰・下堰)に少しずつ注いで降雨を祈ったとも。
中堰は小北の日影神社付近。下堰は日影公民館付近である。
現在(といっても、1987年当時だが)、日影では雷友会(らいゆうかい)という老人会の人々が正月の初日の出を見に、雷電山に登る程度であるという。
玉川村教育委員会編「玉川村植物誌」(玉川村、1995年)によると、「旧日影村には、雷電山から行風山にかけての山並みに、広い村持山と呼ぶ共有林がありました。享保5年(1720)の日影村の古文書の中に、田畑肥(こやし)所の草を刈って肥料にしていることが記されています。村持山の中に田畑肥所という採草地が広く存在していたのでしょう。現在、村持山であった所は皆森林になっていますが、中にかつて草地であったことを想像させる所も残っています」と記されている。
同じく「玉川村植物誌」によると、日影から雷電山を経て、旧雲河原村へ、さらに慈光寺へと通じる道」が記録されている。
現在、雀川砂防ダムから雷電山へ登る道が良く整備されている。
この道が、日影から慈光寺へ向かう古道であったことを示している。
らいでんやま 雷電山(小川町)
比企郡小川町上古寺・腰越
第9回「慈光寺と都幾山・金嶽・士峰山」
2万5千分の1地形図「安戸」
金嶽川とそれに沿って走る県道西平小川線の西側に、上古寺の雷電山から士峰山にいたる顕著な尾根がある。
しかも、この尾根筋は何と風早山(平萱の三角点)まで延々と延びている。
雷電山(280.1㍍4等三角点。点名は「向山」)に登るためには、小川町駅前から東秩父村方面に行くバスに乗り、「パトリアおがわ」バス停で下車。
小川町総合福祉センター(パトリオおがわ)から矢岸橋で槻川を渡り、眼前の腰越と下古寺境界尾根の末端に取り付けば良い。
もっとも、雷電山~士峰山~ショウジバ(赤木)に行くだけなら行程に余裕があるので、松岡醸造を経由して、下古寺の鎮守・天神天満宮をへて、今は入口が鉄柵で閉鎖されている下古寺の古寺鍾乳洞開口部を見てから、その先で尾根にとりつく小道を探しても構わない。
雷電山(上古寺池田)は既に上古寺の領域である。
山頂には山名から想像される雷電神社の痕跡は何もない。
しかし、もともと山頂には落雷を防ぐ目的のための雷電神社の小祠が祀られ、江戸末期には雨乞いも行わていたようである。
だが、明治の神社統合により、雷電神社は村社(鎮守)の氷川神社に合祀され、雷電山の小祠は取り払われた。
今は雷電山の名のみ残る展望のない寂しい山だが、ハイカーの間では雷電山よりも「古寺山」の名の方が一般的である。
山頂にも古寺山なる山名表示版があるようだ。
しかし、古寺山なる呼称が果たして雷電山の別称として地元で通用しているかどうかとなると、極めて疑わしい。
かつて雷電神社が祀られていたからといって、何の変哲もないヤブ山に果たして「古寺山」なる名をつけるだろうか。
おそらく「古寺山」はハイカーのつけた便宜的な仮称で、「古寺山」の私設山名表示板の写真がネットを通じて拡散した結果、「古寺山」の名が広がったのではないだろうか。。
らいでんやま 雷電山(東松山市)
東松山市大谷
初出
2万5千分の1地形図「東松山」
東松山市北部の大字大谷(おおや)にある標高97㍍ほどの小山。
山頂に大谷の鎮守である「大雷神社」の立派な社殿が建てられている。
『新編武蔵風土記稿』比企郡大谷村の条に、「雷電社 雷電山と号せる山の上にあり。村内の鎮守なり。村持」と記録されている由緒ある神社である。
「大雷神社の祭神は人雷命で、水の神様である。大谷地区は水利が悪く、人雷命を祀って降雨祈願を行っていた。江戸時代、豊作の祭礼には江戸から力士を招いて奉納相撲が盛大に行われていたという」(現地の案内板による)。
雷電山(大雷神社)へのルートは2つある。
1つは、古くからの参道である。雷電山南側の県道福田鴻巣線を中内出バス停で下り、荒川の支流・角川を石の橋(神橋)で渡ると、一の鳥居と灯籠がある。
鳥居を抜けると、すぐに車道になり、左は川越カントリークラブである。
まもなく、クラブハウスへの広い車道にぶつかり(これが2番目のルートである)すぐに車道右側の小道の入口に「雷電山古墳」(大雷神社)の標柱、大雷神社の社号標と幟立てがたち、その奥に二の鳥居が見える。
これが参道である。
二の鳥居を抜けると、すぐに石段となり、石段を登り切ると、大雷神社の社殿が建つ雷電山の山頂につく。
2番目のルートは、雷電山東側の県道大谷材木町線の大岡小バス停で下り、大岡小学校の向かいにある川越カントリークラブのクラブハウスへの進入路に入る。
すぐに、入口に「雷電山古墳」の標識、大雷神社の社号標、幟立てのある先の参道が右に分かれる。
最初のルート(一の鳥居からのルート)が正規の参道だが、後者の方が距離が短いし、分かりやすい。
ともあれ、今や大雷神社(雷電山)は川越カントリークラブの敷地内(残存樹林)となっていて、自由に入ることはできるが、すぐそばからゴルファーの声が聞こえるなど、昔の深遠な雰囲気は失われている。
最後に、雷電山周辺の丘陵には、大雷神社のある雷電山古墳をはじめ、三千塚古墳群と呼ばれる古墳群があったが、川越カントリークラブ造成により、大半の古墳が破壊されてしまった。
り
りゅうごっぱな リュウゴッパナ(東秩父村)
秩父郡東秩父村安戸
第7回「笠山前衛の山々」
2万5千分の1地形図「安戸」
笠山から北に延びる尾根の1つである「ツルキリ」(ツルキリ山)~物見山の尾根。
このうち「ツルキリ」から東に少し進んだところにある493.8㍍3等三角点峰(点名は「竜ヶ鼻」)。東秩父村安戸の山である。
「帯沢」(東秩父村安戸)や「松ノ木平」(東秩父村安戸)から眺めると、山頂付近の岩場の形が竜の鼻に似ているところから竜ヶ鼻と呼ばれたが、呼称は「リュウガハナ」ではなく、「リュウゴッパナ」である。
「竜ヶ鼻」(リュウガハナ)が訛って「リュウゴッパナ」の呼び名が一般化したのかと思っていたが、住民は素朴に「リュウゴッパナ」と愛称していた。
そのため、竜の鼻に似た岩場の山から「リュウゴッパナ」の山名が生まれ、それに漢字の「竜ヶ鼻」を宛て字したのかも知れない。
リュゴッパナは、比企・外秩父の孤高な奇峰の雰囲気を醸し出す岩峰だったが、現在は林道が取り囲み、雰囲気を台無しにしているのが残念。
ところで、東秩父村御堂の萩ノ平からは、ツルキリが邪魔になって、リュウゴッパナの岩峰を望むことができない。ただし、リュウゴッパナの呼び名は、萩ノ平でも通用している。
また、リュウゴッパナには、岩松を採りに来た村人が山頂の岩場から転落して死亡したという話が残っている。
りょうとうあんぬま 両頭庵沼(滑川町)
比企郡滑川町中尾(加田地区)
第13回「大立山・二ノ宮山・高根山」
2万5千分の1地形図「武蔵小川」
比企郡滑川町東部を代表する山のひとつ大立山(112.7㍍4等三角点:点名「大立山」)。
その大立山東山麓にある滑川町大字中尾の加田(がだ)集落。
大立山頂の山ノ神を信仰している集落である。
加田集落から大立山に登る手前に大小2つの灌漑沼がある。
これが「両頭庵沼」(りょうとうあんぬま)である。
この沼には竜神(双頭の大蛇)が棲んでいるので、水が絶えたことがなかったという。
沼は二つからなるが、東側の大きな沼(下沼)の奥に気になる二つの碑がある。
右の碑は表面に「真龍軒信道居士 静龍軒妙家大姉 胎児」、裏面に「大正5年9月8日 小高常五郎 小高豊吉建立」とある。
そして、左の碑面には「心中妙真倦」(裏面には、大正4年5月15日 施主小高豊吉)とあるではないか。
この心中碑の由来を加田の集落で尋ねるうちに、両頭庵沼(用土庵沼)にまつわる以下のような悲話(伝説)を採集することができた。
昔この碑のある場所の奥に、若い僧が「用土庵」という名の庵を建てて住んでいた。
この僧と村の娘が恋仲になり、娘は僧の子を身ごもってしまった。
しかし、娘は慶徳寺の方丈と婚約していたので、僧と娘は将来をはかなんで沼に身を投げ、心中してしまった。
心中碑は、二人の悲恋を憐れんで、その霊をなぐさめるために昔、用土庵があったところに建てたという。
また、「両頭庵」の名称由来となっている次のような伝説もある。
昔、沼のほとりに坊さんが「用土庵」という庵を建てて、村人の信望を集めていた。
ある時、ひどい旱魃があり、村人は坊さんに降雨の祈願をお願いした。
坊さんは祈願を引き受けたが、「これから七日七夜の間、絶対にお堂に近寄ってはならない」といった。
ところが、五日目の晩に五兵衛さんという村人がしびれをきらしてお堂の中を覗いてみると、頭が二つある大蛇がとぐろを巻いているではないか。
覗かれたことを知った大蛇は、怒って庵を壊して外に飛び立ってしまった。
それから三日三晩降雨が続いたため、村人は用土庵を両頭庵と名付けるようになった。
心中悲話や竜神伝説を秘めた両頭庵沼であったが、大立山を含むゴルフ場(おおむらさきゴルフ倶楽部)の造成にともない、ゴルフ場の調整池(灌漑池を兼用)に造り変えられてしまった。
わ
わしまるさん 鷲丸山(寄居町)
大里郡寄居町富田(とみだ)
第3回「金勝山とその周辺」
2万5千分の1地形図「寄居」
2万5千分の1地形図「寄居」の右下をみると、国道254号と東武東上線にはさまれた巨大な工場用地がある。
「本田技研工業(株)埼玉製作所 完成車工場」である。
ここが、2008年までこの地に存在していた「鷲丸山」(わしまるさん)の跡地である。
鷲尾山は、金勝山から北に続く尾根の最北端に存在していた山。
標高は216㍍(以前の寄居町地図による)で、『新編武蔵風土記稿』男衾郡富田村や『武蔵通志』にも記載のある浅間信仰の山であった。
小川町勝呂から寄居町富田まで延びる金勝山丘陵は、六反田の沼と炭窯の沼(いずれも水田用の灌漑沼)を結ぶ道を境に北部と南部に分かれる。
南部はもちろん前金勝・裏金勝・西金勝などの金勝山一帯(小川町)。
それに対し、規模や標高において南部に劣るとはいえ、それでも95㌶(東京ドーム20個分以上)規模の丘陵が北部(寄居町)で、北部の頂点が鷲丸山であった。
鷲丸山は、早くも江戸期の『武蔵風土記稿』男衾郡富田村の条に、「鷲丸山 山上に富士浅間の小祠あり」と記録されている。
明治期の『武蔵通志』は以下のように詳細に記している。
「鷲丸山 高さ二百九十尺。男衾郡富田村の南にあり、一峰突兀として聳へ、中腹に小御嶽社あり。社左に烏帽子岩右に亀岩あり。字西小林より上八町四十間。路に釈迦岩あり、頂に浅間神社を安ず。途上富嶽を望むを以てなり」と、山頂の浅間神社や中腹の小御嶽神社、さらに山頂や山中にある奇岩や浅間信仰の由来などが、細かく記録されている。
ここからも分かるように、鷲丸山はその特異な山容や山中にみられる奇岩などにより、古くから地元・寄居町富田の人々により神聖視され、それに浅間信仰が加わり、長くにわたり、親しまれた山であった。
山麓の寄居町富田や北側の金勝山から眺める鷲丸山は、周囲の丘陵のなかで一際高く聳え、さらに山頂部の岩場を突き上げた独特な山容で、一度見たら忘れることのできないインパクトをもっていた。
もし金勝山から鷲丸山を経て、天神山から男衾駅に至るハイキングコースが整備されたならば、穏やかな金勝山と岩場やヤセ尾根など変化に富んだ鷲丸山とのコントラストが楽しめるコースとして、多くのハイカーを迎えたかもしれない。
それこそ先祖代々守ってきた信仰の山を、本田技研工業(株)埼玉製作所寄居工場(2013年7月稼働。2022年1月に閉鎖された狭山完成車工場の分を統合し、埼玉製作所完成車工場として、ホンダの四輪車制作の全国の拠点化)建設のためにいとも簡単に破壊してしまう行為には言葉がない。
ホンダ誘致の計画は工場建設が始まった2007年秋より前から本格化していた。
鷲丸山の破壊と工場用地の整備、工場の建設等を担当した清水建設は、1991年年3月に既に環境影響評価準備書を埼玉県に提出している(「寄居町富田地区工業用地造成事業に係る環境影響評価準備書」清水建設、1991年3月)。
というのは、環境アセス前の事前協議やそれ以前の埼玉県や寄居町による誘致ははるか前から行われていたことが分かる。
準備書の記述を要約すると、埼玉県は県北地域において先端技術を導入して産業の発展を図ることをめざした「テクノグリーン構想」を策定。
これを受け、寄居町は第3次寄居町振興計画基本構想中で、優良企業を誘致し、雇用の場の確保と産業の活性化により、21世紀には5万人都市になることをめざした。
寄居町はさらに1987年に「グリーンバレー構想」を県の協力を得て策定。
その具体化の一環として、清水建設が工業用地の開発計画を町に提案。
寄居町は清水建設による提案を検討し、様々な観点から協議を行ったうえ、地元住民(富田)の強い希望と積極的な賛同が得られ、「グリーンバレー構想」に合致するとの結論が出され、清水建設の工業団地造成計画が寄居町により採用されることになった。
私が鷲丸山を最初に訪ね、おそらく同山を最初に紹介した記事(奥武蔵研究会会報
『奥武蔵』241号、1988年3月所収の山行報告「金勝山・鷲丸山」、『新ハイキング』1988年4月号所収の「金勝山から鷲丸山」)を発表した1988年3~4月当時に、既に開発に向けての動きが始まっていた。
そう思うと、やり切れない心境である。
それでは、在りし日の金勝山か鷲丸山へのコースを1988年3~4月当時の記事を要約しながら、まとめてみよう。
小川げんきプラザのある西金勝横の広場から北によく整備された道をくだる。
国道254号線へ下る車道と分かれ、小川バイパス金勝山トンネルの上を通り、金勝山と鷲丸山との鞍部である六反田の沼と炭窯の沼を結ぶ道に出る。
ここまでは明瞭な道だったが、鷲丸山に向け登り始めると、すぐに踏跡が不明瞭になる。
それでも高みをめざして急登すると、鷲丸山の南肩。北には鷲丸山の山頂が、ひときわ高く聳え、登高欲をそそる。
狭い山頂の北側は一気に切れ落ちた崖で、この方向だけが立ち木が消えて眺望がきく。
前に低くうずくまる上郷(大字富田)の天神山の向こうに熊谷の市街が広がり、はるか彼方には榛名、赤城、日光連山から筑波山までの大パノラマが展開する。
鷲丸山の山頂中央には北に面して「鷲丸山浅間神社 谷津郷中」と彫られた高さ約70センチの石碑(幅は最も広いところで約50センチ、厚さは7センチ)が立っている。
山麓の谷津や塚越(いずれも寄居町大字富田)から仰ぐ鷲丸山は、台地状に盛り上がった基部の右端にピラミダルな岩峰を突き上げた特異な山容で、いかにも神宿る山のイメージにふさわしい。
そう考えると、鷲丸の「マル」は聖なる山を形容する言葉であり、まるでワシが翼を広げたような特異な山容とあいまって、山頂直下の岩壁こそ神が天から降りてくる岩座(いわくら)に見立てられ、ワシマル山の名が生まれたのではなかろうか。
そして、「マル」が朝鮮語にルーツをもっているとするなら、寄居町富田の鷲丸山の名は、寄居町立原の車山と同様、古代この男衾の地に移住してきた渡来系氏族によって命名された可能性も出てくる。
浅間信仰の盛んな時代、例祭の日になると山頂の直下には露天も出て大いに賑わったという。
谷津の集落から沢沿いに山頂の東側鞍部に登る道が鷲丸山の「本通り」とされ、小川町木呂子との境付近から登る「裏通り」と合わせ、多数の登拝者を迎えた。
鷲丸山の周辺には炭窯の沼や六反田の沼など大小いくつもの灌漑用の沼が散在するが、これらの沼を総称して「富士五湖」と呼んでいたという。
いずれも、1988年から遡って40年以上前(現在=2024年から遡ると、80年以上前)の話だ。
山頂をあとに、東に岩混じりの急降下。
途中に「薬師嶽薬王神社」の石碑もみられ、神域の雰囲気が伝わってくるようだ。
鞍部から戻り気味に山頂直下の岸壁の基部を巻く。この付近で東側の谷から登ってくる「本通り」が合流するはずだが、廃道になって久しいせいか、路形すら見当たらない。
山頂から北に延びる尾根に出ると、やせ尾根の急下降になり、200㍍そこそこの山とはとても思えない高度感だ。
まもなく自然地形を利用した小高い富士塚の上に、高さ約1.3㍍の細長い石碑が立つ。表面には「朝日浅間大神」とあり、裏面に「明治17年3月 富田村吉田恵輔」の銘があり、かつてこの地にあった社を再建し、養蚕や安産の神様として祀った経緯が判読できる。
この「朝日浅間」が『武蔵通志』のいう「小御嶽社」に当たるものかどうかについては、残念ながら確認するにいたっていない。
再び急激にくだり、最後の登りを終えたところが167㍍独標で、真新しいコンクリート製の山ノ神の小社が祀られている。
祠の前からくだる明瞭な道を急降下5分で、沢沿いの「本通り」と合流。
谷津の集落に出る。
ところで、奥武蔵研会員会員の町田尚夫氏は、ホンダ技研工業が鷲丸山一帯の約95㌶もの用地を買収し、工場を建設することが明らかになって以降、2006年10月から2007年10月までの1年間に5回も鷲丸山を訪れ、かつての浅間信仰の山の終焉と山中の石碑群のその後を記録した(奥武蔵研究会会報『奥武蔵』409号、2016年5月所収の「懐想の鷲丸山」)。
同記事によると、2007年10月には、鷲丸山山頂にあった「鷲丸山浅間大神」の石碑が抜き去られ、跡にポッカリと穴があいている状況を撮影している。
そして、山中の石碑群の最初の移設地を訪ねている。
さらに、2016年1月に最終的に石碑群を遷座した地(鷲丸山山域跡の本田技研(株)埼玉製作所 完成車工場の北の一角)を確認して、入口に立つ黒御影の碑に刻まれた遷座の記を忠実に書き写している。下に引用しておこう。
「遷座の記 武蔵の國男衾郡富田の地に太古より聳え立つ鷲丸山は山頂に浅間社の祠を建立し江戸時代より現在に至って来たがホンダ技研工場寄居工場の立地計画により山中に散在した鷲丸山浅間社を始め数祠と供養塔を平成21年4月当所に遷座した
谷津地区の海抜212米の霊山は其の姿を消し再び見る事はないが誠に痛惜の念を禁じ得ない
祭神の氏子達の末永き御加護を祈願する
平成21年7月吉日
小被神社宮司 持田倫武撰文
江戸時代より浅間信仰の山として親しまれてきた「オラが山」を、雇用や税収のためとはいえ、現在の住民だけの意思でデベロッパーに売り渡し、後生の人々が再び見ることができない状況を生む権利が果たして私たちにあるのだろうか。
そんなこと考えさせる「前座の記」である。
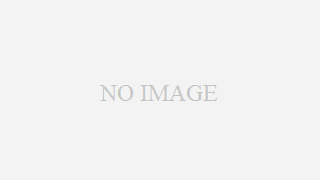

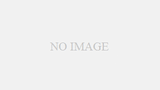
コメント