比企・外秩父の気になる山や峠を手っ取り早く知りたい方のために、「比企・外秩父の山徹底研究」14回連載のエッセンスに未紹介の山を加えたコンプリートな小辞典をつくってみました。
山名については、その由来を記すことにし、峠名・巨石名のほか、重要な地点名も数カ所取り上げました。
「愛宕山」「物見山」など同名の山がいくつもある場合は、標高の高い順に掲載しています。
以下凡例を示しますが、山名・峠名についてもっと詳しく知りたい方は「徹底研究」の該当回をご参照ください。
また、各項目をカバーする国土地理院発行2万5千分の1地形図を挙げておきますので、2万5千分の1地形図および昭文社・山と高原地図23『奥武蔵・秩父』(奥武蔵研究会調査執筆)を見ながら読み進めると、良く分かるでしょう。
まず「あ行」からスタートし、今後月2回程度のペースで順次追加するとともに、誤植や誤り、不十分な点などを随時訂正します。
誤りを発見したり、疑問点があれば、「問い合わせ」を使ってご指摘いただければ幸いです
(凡例)
見出し
かさやま 笠山(小川町・東秩父村)
本文
比企郡小川町腰越・秩父郡東秩父村白石
第8回(笠山・堂平山)
2万5千分の1地形図「安戸」
説明文
○○○・・・
それでは、比企・外秩父のディープなワールドに浸ってください。
あ
あきばさんじゃくぼうあと 秋葉三尺坊跡(寄居町)
大里郡寄居町大字富田字上郷
第3回「金勝山とその周辺」
2万5千分の1地形図「寄居」
小川町の金勝山(きんしょうざん)北側にあった鷲丸山(わしまるさん)を造成してできた「ホンダ埼玉製作所 完成車工場」(寄居町富田谷津地区)の北にある天神山丘陵(寄居町富田上郷地区)のピークにある「秋葉三尺坊」の跡地。
山稜の東にある180㍍独標の西側ピーク上。
丸太のベンチのある山頂には「大山祇命(オオヤマヅミノミコト)の小さな碑が立ち、その背後に約1メートルの盛り土がある。
これが「秋葉三尺坊跡」であり、かつて火伏せの神である秋葉三尺坊大権現を祀った社殿ないし大きな石碑が建立されていたと思われる。
あたごやま 愛宕山(東秩父村・皆野町)
秩父郡東秩父村坂本・秩父郡皆野町三沢
第11回「二本木峠・皇鈴山・登谷山
2万5千分の1地形図「寄居」
二本木峠のすぐ北にある654.9㍍3等三角点峰(点名は「二本木」)。
純林が茂って展望のない山頂には、愛宕神社の石碑がたたずんでいる。
あたごやま 愛宕山(小川町・東秩父村)
比企郡小川町勝呂・秩父郡東秩父村安戸
第2回「官ノ倉山西尾根とその周辺」
2万5千分の1地形図「安戸」
官ノ倉峠から西に延びる官ノ倉西尾根と入山川に沿って城山(安戸城址)から西に延びる尾根が合流する410㍍圏ピーク。
細窪山(421.2㍍三角点)のすぐ東側のピークである。
愛宕山は小川町勝呂側の呼称。
南北に細長い山頂の北肩に勝呂の宮沢家が明治18年(1885)4月に奉納した瓦屋根の愛宕神社の小祠があったが、今は破損しているのが残念である。
あたごやま 愛宕山(東秩父村・寄居町)
秩父郡東秩父村大内沢・大里郡寄居町西ノ入
第2回「官ノ倉西尾根とその周辺」
2万5千分の1地形図「安戸」
「金山」(かなやま)の別称→「金山」の項を参照
あたごやま 愛宕山(東秩父村)
秩父郡東秩父村安戸
第1回「官ノ倉山とその周辺」
2万5千分の1地形図「安戸」
東秩父村安戸から小川町腰越の小瀬田に越える峠である「小瀬田越え」のすぐ西にあった250㍍圏ピーク。
山頂に愛宕神社の小祠が祀られていた。
安戸の宿地区の人々により火伏せの神として信仰され、4月29日が例祭だったが、東秩父カントリークラブ造成工事にともない、小瀬田越えとともに造成され、消滅した。工事は途中で中止となり、周辺は広大な草原となっている。
あたごやま 愛宕山(小川町)
比企郡小川町下里
第5回「遠ノ平山とその周辺」
2万5千分の1地形図「武蔵小川」
観音山(大聖寺のある山)から西に延びる尾根上にある170㍍圏ピーク。
山頂には下里下分(下里1区・2区)の信仰を集める愛宕神社が鎮座。
信仰の盛んなときには、旧暦の8月25日に祭りが行われ、神社の前で老若を問わず相撲好きの人々が集まって祈願相撲が行われ、餅も配られたという。
あたごやま 愛宕山(ときがわ町)
比企郡ときがわ町本郷
第6回「雷電山・御岳山・大峰とその周辺」
2万5千分の1地形図「武蔵小川」
八高線明覚駅のすぐ北西にある160メートル独標。
かつて山頂には愛宕神社の小祠があったが、明治末に山麓の春日神社に合祀され、今は山頂には何もない。
あたごやま 愛宕山(寄居町)
大里郡寄居町鉢形
初出
2万5千分の1地形図「寄居」
東武東上線鉢形駅南方の小ピーク。
約300段の石段を登った山頂には愛宕神社が祀られている。
愛宕神社の鐘は明治の文人・田部里風(たねべりふう)の「鉢形八景」にも「愛宕山晩鐘」として描かれるほど有名だったが、太平洋戦争末期、軍に徴用され亡失した。
現在の鐘は、地元出身の実業家・雨宮三兄弟が昭和33年(1958)に寄進したものである(町田尚夫『奥武蔵をたのしむ』さきたま出版会、2004年)。
愛宕山は、豊臣軍による鉢形城攻撃の際に、車山とともに攻撃の要衝となった。
現在は、寄居町のハイキングコース「愛宕山コース」として良く整備されている。
あまごいやま 雨乞山(小川町)
比企郡小川町勝呂
第1回「官ノ倉山とその周辺」
2万5千分の1地形図「安戸」
東武東上線の線路をはさんで「金勝山」(きんしょうざん)の南に対峙する山。
2万5千分の1地形図「安戸」では、「勝呂」の表記のすぐ下にあった山。
地形図での変遷を見ると、当初は採石場の上にかろうじて250㍍独標が残っていたが、
徐々に採石場の範囲が拡大。
最新の地形図では250㍍独標は姿を消し、山は完全に削られ、削平されており、調整池らしきものができている。
雨乞山は完全に消滅したといってよい。
山麓には津島神社がある。
悲しい最期を遂げた雨乞山だが、戦前まではその名のとおり小川町勝呂の雨乞いの山であった。
田植え前に日照りが続いたとき、上勝呂・下勝呂から2名ずつの計4名の代表が榛名神社に行き、一升樽に御水をもらい、地元に運んで戻ったあと、待っていた集落の代表と一緒に雨乞山に登り、水を撒いて降雨を祈願し、一同酒を飲んだ。
代表たちが下山したのち、村人たちは津島神社の祭神である「素戔鳴尊」(スサノオノミコト)、「天照太神」(アマテラスオオミカミ)の二体の木造のご神体を山車に乗せ、蓑笠をつけて太鼓・鉦(かね)を叩き、総出で夜遅くまで練り歩いたという。
い
いしぶねやま 石舟山(小川町・東秩父村)
比企郡小川町腰越・東秩父村安戸
第7回「笠山前衛の山々」
2万5千分の1地形図「安戸」
比企を代表する名山「笠山」から北東に延々と延びる長大な比企郡・秩父郡の郡界尾根が槻川河原に尽きるの最後の盛り上がりの山。標高230㍍圏。
山頂は樹木で覆われ、展望はないが、石舟神社の祠があり、その前に大小の石舟が2基奉納されている。
石舟神社は山麓にある腰越の関根家の氏神であり、雨乞いに霊験のある神様として、腰越の人々の信仰を集めていた。
雨乞いが行われたのは昭和の初め頃までで、夏に日照りが続き、畑に被害が出るようになると、腰越では村中総出で雨乞いを行った。
まず腰越の村社である氷川神社の神官を先頭に集落の人が関根家にあるご神体の大小2本の棒(舟を漕ぐ櫓)をもち、山に登り、大小2つの石舟にご神体の大小2つの坊をそれぞれ乗せたあと、山をくだり、地元の力持ちが石舟様を,担ぎ下ろし、切通橋付近の河原に安置。
そののち祈祷が始まり、やがて神官が川に入ると、祝詞を奏上する神官めがけて氏子たちが水をひっかけ、降雨を祈願した。
長らく腰越では行われなかった石舟神社の雨乞いを、東秩父村安戸の帯沢・寺岡の人々が1975年5月25日に復活させたが、今でも続いているだろうか。
お
おおいぬあな 大犬穴(寄居町)
大里郡寄居町西ノ入
第2回「官ノ倉西尾根とその周辺」
2万5千分の1地形図「安戸」
『武蔵国郡村誌』『武蔵通志』は、いずれも「大犬穴山」と記載。
しかし山ではなく、山中にある巨岩である。
場所は、西ノ入の五ノ坪川に沿った林道をつめ、ヒノキの山林を登るようになったら、山腹の斜面に高さ8㍍ほどの石灰岩の巨岩がのしかかるように周囲を圧倒している。
これが「大犬穴」である。
昔オオカミが棲んでいたという「大穴」があることから、「大犬穴」と呼ばれるようになったという。
そのまま山林をつめて小尾根に出たら、さらに登り切ると、官ノ倉西尾根の「細窪山」西にある比企郡・秩父郡・大里郡三郡の境界にあたるピーク(「三郡境」と便宜的に呼称)に出る。
おおぎりやま 大霧山(東秩父村・皆野町)
秩父郡東秩父村皆谷・秩父郡皆野町三沢
第10回「新定峰峠・旧定峰峠・大霧山・粥新田峠」
2万5千分の1地形図「安戸」
粥新田峠(かゆにたとうげ)の南にある766.7㍍3等三角点峰(点名は「大霧山」)。
山頂からは360度の大展望が得られる。
山名の由来は、『新編武蔵風土記稿』秩父郡三沢村の条に「ややもすれば雲霧を含み、頂を蔵せり」とあり、『武蔵通志』でも、「山頂雲霧常に絶えず、故に大霧の名あり」とあるように、霧が立ち込めることが多い山ということに由来するというのが定説である。
しかし、周囲には標高が同じ程度の山もあり、気象条件的にもとくに大霧山だけが霧が発生しやすいというわけではない。
この説はむしろ「大霧山」という漢字表記に付会した説であろう。
むしろ、「キリヤマ」が「開墾地」「焼畑」を意味することと、山の東側が秩父高原牧場であり、その前身の大規模な開墾地があったことから「大キリ山」の名が生まれ、それに「大霧山」の字をあてたことから、「山頂がつねに雲や霧に包まれている」という山名由来が生まれたのではないだろうか。
なお大霧山の山頂には、小川町下古寺の「古寺鍾乳洞」に続くといわれる深い穴があるという。
おおだてやま 大立山(滑川町)
比企郡滑川町中尾
第13回「大立山・二ノ宮山・高根山」
2万5千分の1地形図「武蔵小川」
「二ノ宮山」「高根山」とともに、比企郡滑川町を代表する山。
滑川町大字中尾加田(がだ)集落のため池「両頭庵沼」の背後にある。
山頂には南から112.7㍍4等三角点(点名は「大立山)標石、安永4年(1775)2月吉日記銘の山ノ神の小祠、冨士浅間太神・小御嶽神社の石碑がある。
山名は、山麓の加田集落にある加田薬師付近から眺める堂々たる山容によるという。
以前は山頂に松の大木があり、良く目についた。
男松2本、女松1本が、女松を真ん中にしてそびえたっており、大立山のシンボルとなっていたが、残念ながら台風で倒壊してしまった。
大立山の山ノ神は加田集落の信仰を集めている。
毎年1月17日が山ノ神の祭り(初詣)で、加田集落のうち昔から住む15軒の人々が登拝する。
当日は午前10時頃に山頂に登り、山ノ神の祠に餅を2つ供える。
拝んだあと、供えた餅のうち、1つを残し、他の家が供えた餅のうち1つをもらって帰り、餅の取り替えっこを行う。
もらってきた餅を食べると、山仕事をしていてもマムシにかまれないという。
しかし、大立山から二ノ宮山にかけての一帯が、西武鉄道の「滑川嵐山ゴルフコース」(現・おおむらさきゴルフ倶楽部)の計画地になってしまった。
大立山は残存樹林として残ったものの、ゴルフ場内になり、地元・加田集落の人々も、年に1回、1月17日の初詣のときにしか登ることができなくなった。
おおびらやま 大平山(長瀞町・寄居町)
秩父郡長瀞町岩田・大里郡寄居町風布
第12回 地形図「釜伏峠・葉原峠・大平山・金ヶ嶽・金尾山」
2万5千分の1地形図「寄居」
葉原峠の北にある538.6㍍3等三角点(点名は「小林山」)ピーク。
山頂のすぐ北側がゴルフ場(長瀞カントリークラブ)。
寄居町の風布から眺めると、台地状の堂々たる山容が印象的である。
この山容と風布、金尾、岩田、井戸などにまたがる根張りの大きな山容から大平山(おおびらやま)と命名されたと推察される。
すぐ南の葉原峠にはハイキングコースが通っているが、そこから外れた不遇な山。
「小林山」と呼ぶ向きも多いが、「小林山」は寄居町風布の小林地区みかん山の総称名であろう。
むしろ『武蔵通志』で「土鍋山」(つちなべやま)あるいは「指山」(さすやま)と呼ばれている山が「大平山」であろう。
「指山」の「サス」は焼畑をさす地名であり、昔この付近が焼畑であったことを想像させる。
「土鍋山」(つちなべやま)は、長瀞町岩田付近から望む土鍋(どなべ)に似た山容によるものと思われる。
おおひらやま 大平山(嵐山町)
比企郡嵐山町遠山・千手堂
第4回「仙元丘陵」
2万5千分の1地形図「武蔵小川」
嵐山渓谷の北側にある179㍍独標。
山頂一帯は武蔵嵐山公園として整備されており、四方から山頂に遊歩道から登っている。
山頂からの展望は素晴らしく、眼下に嵐山渓谷を一望できる。
山頂には、かつて小倉城の物見櫓があったと伝えられるほか、雷電神社が祀られていることから、かつては雨乞いが行われた場所でもあった。
ところで、『武蔵通志』には「雷電山 高五百尺菅谷村千手堂の西にあり、頂に雷電社あり・・・」と記している。
位置的にも、山頂に雷電神社を祀り、雨乞いの山であったことからも、ここでいう「雷電山」は大平山のことを指すのではないか。
おおみね 大峰(ときがわ町)
比企郡ときがわ町日影
第6回「雷電山・御岳山・大峰とその周辺」
2万5千分の1地形図「武蔵小川」
ときがわ町大字日影の小北(こぎた)集落北にあり、小川町境界にかけて広がる山の総称。
最新の2万5千分の1地形図「武蔵小川」(2017年10月調製、2018年1月1日発行)では、小川町境界上にある293㍍独標に「大峰山」の名が記されており、旧玉川村教育委員会編集の『玉川村植物誌』(1995年3月)でも「大峰山」の名を使っているが、山の所有者に確認したところ、正しくは「大峰」である。
また「大峰」は、293㍍独標単独の名称ではなく、小川町境界の同峰を北峰とし、283㍍独標を南峰とし、中間のピークを中峰とするおおむね3つのピークの総称である。
『玉川村植物誌』によると、大峰の写真を載せ、その説明として「日影の集落から見た大峰山です。なだらかな山で、昔から山腹にたくさんの切畑や山畑が作られ、利用されてきたようです。山頂部は採草地として草地に利用されてきたことが、明治の地図からわかります」とある。
大峰の山頂部が草地で展望が良かったことは、かつて大峰の所有者にインタビューしたしたときにも、「空気の澄んだときには、山頂から東京タワーまで望見できた」との言葉からも裏付けられる。
所有者によると、大峰の名称は、村(日影村)の北境にそびえる雄大な山容によるもの(ひときわ目立つもの)であろうということであった。
なお、大峰から北に尾根続きの小川町側の丘陵(福寿山と総称)も、大峰と同じく山頂部は草地で展望が良く、大峰のすぐ北側は「富士見平」(字名)と呼ばれるほど富士山の眺望が良かったという。
しかし、小川町側の福寿山(総称)は、御岳山を除き、「(仮称)武蔵台カントリークラブ」(現・アドニス小川カントリー倶楽部」)の造成により完全に破壊されてしまった。
大峰北峰(293㍍独標)にも山頂直下までゴルフ場が迫り、景観は一変してしまった。
おぐらじょうし 小倉城址(ときがわ町・小川町)
比企郡ときがわ町田黒・比企郡小川町下里
第4回「仙元丘陵」
2万5千分の1地形図「武蔵小川」
小倉峠から登りに転じる仙元丘陵が槻川の曲折部に急激に落ち込む手前に、尾根に忠実に沿って遺構のある城跡。
小倉城の城主としては、小田原北条氏の家臣・遠山右衛門太夫光景という説が有力である。
近くの遠山寺(嵐山町遠山)には光景の墓があり、小倉城の大手門入口にあたる大福寺(ときがわ町田黒)には、光景内室の位牌が保管されているという。
豊臣秀吉の小田原征伐のとき、小田原城の重要な支城であった松山城が落城したとき、小倉城も運命ともにしたという。
だが、小倉城の城主については、松山城主の上田氏とする説もあり、確定していない。
2008年3月28日、既に国の史跡に指定されていた菅谷館跡(嵐山町)、松山城址(吉見町)、杉山城址(嵐山町)に小倉城址も追加され、4城館一括で「比企城館跡群」の名で国指定の史跡になった。
それ以降、小倉城址の整備も進み、今では麓の大福寺横に駐車場のある立派な入口と遺構図およびその説明があり、山に入ると、道が整備され、要所要所に説明書きがある。
小倉城は天然の要害を最大限利用している。
仙元丘陵の地形に沿って郭(くるわ)が築かれ、北の槻川への急崖は天然の要害になっている。
そのため弱点である西側、つまり小倉峠側からの侵入に備えたつくりになっている。
おぐらとうげ 小倉峠(小川町・ときがわ町)
比企郡小川町下里・比企郡ときがわ町田黒
第4回「仙元丘陵」
2万5千分の1地形図「武蔵小川」
小川町青山の仙元山から城山をへて、252.4㍍4等三角点で直角に右に折れ、槻川右岸に沿って東に延びる丘陵を通称・仙元丘陵と呼ぶ。
この仙元丘陵の東部にある下里の仙元山から南に八高線・明覚駅付近にくだる尾根と分かれ、東に主尾根をくだると、鞍部に出る。
鞍部は十字路になっていて、進行方向から左に下りると、小川町下里1区の東坂下。右にくだると、ときがわ町の小倉集落(大字田黒)。正面に尾根を登ると、小倉城址に出る。
小川町の下里からときがわ町の小倉へ越える峠という意味で、「小倉峠」と呼ばれていた。
おしゃもじやま お杓母子山(鳩山町)
比企郡鳩山町今宿
初出
2万5千分の1地形図「越生」
鳩山町大字今宿にある62.7㍍4等三角点(点名「今宿」)のある小山。
中腹にお杓母子神社があり、大きなしゃもじのご神体が2体奉納されている。
風邪に効能のある神様で、10月15日夜の縁日に例祭が行われる。
山頂には「おしゃもじ山公園展望台」が設けられている。
天気の良い日には遠く筑波山や新宿の高層ビル群、そしてスカイツリーも見えるという(藤本一美「比企の『おしゃもじ山』探検」『新ハイキング』379号、1987年5月)。
駅から歩くと遠いのが難だが、東武東上線坂戸駅北口から大橋行きのバスに乗車。
「公園前バス停」(所要時間約20分)で下りると、「お杓母子山」が目前である。
おだいにちさま お大日様(大日山:ときがわ町)
比企郡ときがわ町日影
第6回「雷電山・御岳山・大峰とその周辺」
2万5千分の1地形図「安戸」
ときがわ町日影の雀川砂防ダムから雀川(行風川)を忠実につめると、雷電山と御岳山を結ぶ尾根に出る。
この地点は行風山(332㍍独標)左のCATVアンテナのあるピーク(320㍍圏)と行風山南の330㍍圏ピークとの鞍部である。
後者の330㍍圏ピークは小広い台地状の山で、雑木の茂る山頂の中央には石塚(石積み)が築かれ、その上には古い石碑が寂しくたっている。
東側山麓の小北(大字日影)で尋ねると、かつて「お大日様」(大日如来)を祀った跡であるという。
日影では、「お大日様」を祀った山ということから、330㍍圏ピークを「大日山」(だいにちやま)と呼ぶ人もいる。
おんたけさん 御岳山(小川町)
比企郡小川町青山「仙元丘陵」
第6回「雷電山・御岳山・大峰とその周辺」
2万5千分の1地形図「武蔵小川」「安戸」
2万5千分の1地形図「武蔵小川」「安戸」で、「大峰山」と記載のある小川町・ときがわ町境界の293㍍独標(「大峰」が正しく、293㍍独標は大峰北端のピークである)北西にある297㍍独標。
小川町青山上にあり、山頂には木造の鳥居の奥に石の台座に乗った明治19年(1886)建立の「御嶽様」(正式には「御岳山蔵王大権現」)の石像がある。
この石像はサイズこそ異なるとはいえ、木曽御岳山の本尊と姿形とも同一であるともいう。
御岳神社(御嶽神社)は「御岳山座生大権現」の名が示すように、神仏習合の名残をとどめており、山号は「福寿山」である。
つまり、「福寿山御岳山座生大権現」が御岳神社(御嶽神社)の本尊である。
御岳山の例祭は4月18日。かつては例祭時に青山上(小川町)だけではなく、上古寺(小川町)、日影(ときがわ町)から、さらに東京からも参拝者があったという。
青山上では、ときがわ町境までに及ぶ南部の丘陵全体を「福寿山」と呼んでいた。
この広義の「福寿山」は、小字「福寿」や「富士見平」を含む一帯である。
福寿山の最高点が御岳山であり、物見山の別称もあったという。
往時の御岳山周辺は草地で展望が良く、御岳山から三笠山(ゴルフ場造成前の1986年測量・同年4月30日発行の2万5千分の1地形図「武蔵小川」で大峰山の名をつけている289㍍独標)、その北の八海山へと御岳山にちなんだ名が付けられ、三笠山・八海山の山頂には同じ形状の石像(三笠山様・八海山様)が祀られていた。
青山上から八海山・三笠山を経由して御岳山に登る道が参道だった。
信仰の厚かった御岳山も、山頂だけを残し、周囲の丘陵は「仮称・武蔵台カントリークラブ」(現・アドニス小川カントリー倶楽部)造成のため、すべて破壊されてしまった。
今残っているのは、御岳山頂と、その北にある神社記号(八坂神社)だけである。
なお、御岳山の南西山腹(小川町上古寺)には、奥ノ院的な存在である「サネ山の奥ノ院」の祠がある。
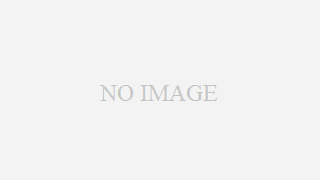

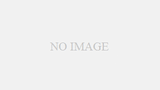
コメント